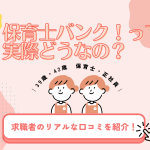五領域の「人間関係」を育むには、どのような遊びを展開すればよいのか、声かけや援助の仕方に戸惑う保育士さんもいるのではないでしょうか。今回は、保育所保育指針をもとに五領域「人間関係」のねらいと内容を解説します。また、援助のポイントや遊びの実践例についてもまとめました。

maroke/shutterstock.com
目次
五領域における「人間関係」とは
まずは、五領域における「人間関係」とはどういうものか、厚生労働省「保育所保育指針」をもとにみていきましょう。
五領域「人間関係」の概要
そもそも五領域は、保育園生活を通して育みたい子どもの能力や態度を、「健康」「人間関係」「環境」「言葉」「表現」の5つの領域に分けて示したものです。
そのうちの一つ「人間関係」は、人との関わりに関する領域についてまとめてあり、 「他の人々と親しみ、支え合って生活するために、自立心を育て、人と関わる力を養う」と示してあります。
子どもたちが周りの人と関わって生きていくための力を養うことが目的となるようです。
五領域「人間関係」のねらいと内容
保育所保育指針では、五領域のねらいと内容を、1歳以上3歳未満児の保育に関わるもの・3歳以上児に関わるものに分けて示しています。
厚生労働省「保育所保育指針」を元に、それぞれみていきましょう。

乳児は、園生活を通して保育士さん以外の友だちに興味を持ちはじめ、友だちといっしょに過ごす大切さを知ったり、生活のルールに気づいたりとさまざまなことを身につける時期といえるでしょう。
自分でなにかしようとする気持ちが盛んになる時期でもあるため、保育士さんは子どもの気持ちを尊重し、あたたかく受け止めていけるとよいですね。
幼児では、周りの友だちとの関わりが大切となるようです。
関わりの中で、自分や友だちのよさを見つけたり、思いを伝え合ったりすることもあるでしょう。
保育士さんが関わりを仲立ちしながら相手の気持ちに気づけるよう援助することで、子どもが自分の気持ちをうまく調整する力を身につけたり、きまりの必要性を知ったりすることにつながるのですね。
五領域「人間関係」の視点のポイント
子どもが保育園で過ごすとき、どのように「人間関係」の能力を育んでいくのでしょうか。
大まかな流れと保育士さんが意識するべきポイントをみていきましょう。

このように、保育士さんとの愛着関係を基盤に、友だちとの関わりが育まれていくという流れがあるようです。
保育士さんは、子どもの発達過程に合わせて必要な声かけをしたり友だちとの関わりを仲介したりといった援助をしていけるとよいかもしれませんね。
【乳児向け】五領域「人間関係」を育む遊びと援助の実践例
乳児クラスにおける、五領域「人間関係」を育むための具体的な遊びや援助についてみていきましょう。
0歳児:ふれ合い遊び
0歳児クラスで、ふれ合い遊びを行なうときのポイントを紹介します。
保育の流れ
「いっぽんばし」や「ラララぞうきん」などのわらべうたを通してふれ合い遊びをしてみしょう。
おなかをくすぐったり、手や足を軽く握って揺らしたりといったふれ方ができるとよさそうです。
ねらい
- 保育者のふれ合いや語りかけをよろこび、安定して過ごす。

子どもは保育士さんとふれ合うことで安心感や心地よさを味わえるでしょう。
そうした経験が保育士さんとの愛着関係の形成につながり、次第に周りの人に興味を持ち関わろうとする意欲が湧くようです。
保育士さんが笑顔で関わることで、子どもの「だれかといっしょに遊ぶことは楽しいな、うれしいな」という気持ちを育めるとよいですね。
1歳児:布団遊び
1歳児クラスで、布団遊びを行なうときのポイントを紹介します。
保育の流れ
布団を敷き詰めたり、なだらかな山を作ったりして環境を整えます。
歩くスペースと寝転がるスペースを分けておくと安全に遊べそうです。
保育士さんの人数に余裕がある場合は、毛布を2人で持ち子どもが乗ってハンモックのように揺らしてみても面白そうですね。
ねらい
- 布団の感触を味わい、保育士と充分にふれ合って遊ぶ心地よさや楽しさを感じる。

「保育士さんと同じ遊びを通して、同じ感覚を共有している」という感覚が、愛着関係の形成にもつながっていくでしょう。
保育士さんは「あったかいね」「ふわふわしてるね」と子どもの気持ちを代弁し、心地よさに共感するのがポイントです。
2歳児:砂遊び
2歳児クラスで、砂遊びをするときのポイントを紹介します。
保育の流れ
園庭に出て、砂場で遊びます。
空き容器やバケツ、スコップなどの道具が破損してないか確認してから用意し、砂場に異物がないか、砂が固まっていないかもチェックしておきましょう。
ねらい
- 砂遊びを通して、保育士や友だちといっしょに遊ぶことを楽しむ。

子どもたちは保育士さんの仲立ちに助けられて、友だちといっしょに遊ぶよろこびを味わえるようになるでしょう。
保育士さんが、子どもの見立て遊びやつもり遊びを共有する言葉がけをすれば、さらに友だちとの関わりが広がっていきそうです。
これらの実践例のように、0歳児や1歳児では、主に保育士さんとの愛着関係の形成をメインに考えられるとよいでしょう。
1歳児の後半や2歳児になると友だちとの関わりや平行遊びも増えてくるかもしれません。
保育士さんが子どもの気持ちを受け止めつつ、周りの人と関わる楽しさを味わえるようにしていけるとよいですね。
簡単1分登録!転職相談
保育士・幼稚園教諭・看護師・調理師など
保育関連の転職のご質問や情報収集だけでもかまいません。
まずはお気軽にご相談ください!
【幼児向け】五領域「人間関係」を育む遊びと援助の実践例
幼児クラスにおける、五領域「人間関係」を育むための具体的な遊びや援助についてみていきましょう。
3歳児:鬼ごっこ
3歳児クラスで、氷鬼を行なう時のポイントを紹介します。
保育の流れ
戸外に出て、ダンスをするなど身体を動かす準備をします。
氷鬼のルールを確認し、保育士さんがオニとなって氷鬼を行ないましょう。
<お約束>
- タッチされたら氷のように固まる
- 固まっても友だちにタッチされることでまた逃げられる
上記のようにあらかじめルールを決めて、遊ぶ前にみんなで決まりを認識できるよいですね。
ねらい
- 簡単なルールのある遊びを通して、その楽しさや決まりを守る大切さに気づく。

最初のうちは、逃げる・追いかけるという先生との1対1の関係を楽しんでいる子どももいるでしょう。
保育士さんは繰り返し遊びを行なう中で、仲間を助けられることを伝えていきましょう。
そうすれば、みんなで一体となって遊ぶことを楽しんだり、ルールのある遊びの面白さを味わったりすることにつながるかもしれません。
4歳児:ルールのある集団遊び
4歳児クラスで、「もうじゅうがり」のゲームを行なうときのポイントについて紹介します。
保育の流れ
1.遊戯室など広いスペースに移動し、遊び方の説明をします。
2.「もうじゅうがり」の歌を歌います。
3.お題となる動物の名前の文字数を数え、その数と同じ人数で集まり手をつないでグループになるよう促します。
(例:「きりん」なら3文字のため、3人で集まります。 )
4.保育士さんは、動物の名前と数が一致するようにタンバリンで音を鳴らし、数を数えられるようにしましょう。
最初は「さる」や「うさぎ」など、簡単な文字数の動物から始めるとよいかもしれません。
ねらい
- ゲームを通して、たくさんの友だちとふれ合うことを楽しむ。

いろいろな友だちと混ざりあってグループを作るので、たくさんの友だちと交流できそうです。
手をつないでふれ合うことで、安心感や一体感を得ることにもつながるでしょう。
保育士さんは、上手くグループを作れず悔しがったり悲しんだりする子どもに寄り添い、励ますことで、安心して遊びを楽しめるようにできるとよいですね。
5歳児:共同製作
5歳児クラスで、お楽しみ会の共同製作を行なうときのポイントについて紹介します。
保育の流れ
1.お楽しみ会の本番で使うためのアーチを作ることを話します。
2.話し合いでは、どんな絵をかくか、どうやって作るか、誰がどこを担当するかなどを決められるとよいでしょう。
3.作っていく過程では、子どもが自発的に始められるように充分な数の道具などの用意をしておきます。
4.他の子どもを誘いかけたり、子どもが思いや考えを伝え合えるような声かけをしたり、見守りつつ適度に関わっていきましょう。
ねらい
- 友だちと協力して一つの作品を作ることで、自分の思いや力を発揮するとともに、友だちのよさに気づく。

話し合いを通して、子どもは相手の気持ちを知ったり、折り合いを付けるための方法を考えたりすることができるでしょう。
保育士さんは、製作の中で友だちの表現のよさに気づけるよう関わるとよいですね。
自分のよさをそれぞれに発揮するだけでなく、お互いのよさを認め合い、力を合わせて活動できるとよいかもしれません。
保育士・幼稚園教諭・看護師・調理師 etc.無料転職サポートに登録五領域「人間関係」を育むための援助のポイント

maruco/shutterstock.com
五領域「人間関係」の能力を育みたいときに、保育士さんの援助のポイントをまとめました。
スキンシップなどを通して子どもと安定した関係を築く
保育士さんとの愛着関係は、子どもにとって安心できる大切な基地の一つとなるでしょう。
子どもの甘えたい気持ちや不安な気持ちに寄り添い、スキンシップを取ったり子どもの気持ちや言葉を代弁したりすることで、信頼感を築けるのではないでしょうか。
保育士さんとの安定した関係ができたあとで、友だちや他の保育士さんとの関係へと広げていけるとよいですね。
保育士が仲立ちとなって子ども同士の関係を築けるようにする
幼児クラスの子どもなどでは、自分の気持ちが上手く表現できなかったり、自我が芽生え自分の思いを通したかったりと、友だちとの関わりの中でトラブルにつながることも考えられます。
保育士さんが「そうだったんだ、○○したかったんだね」とそれぞれの子どもの思いを受け止めたうえで、どうするとよいのか解決策をいっしょに考えていけるとよさそうです。
子どもが自分なりに一生懸命考えたり、思いを伝え合ったりすることで、相手の気持ちに気づき、お互いが納得できる方法をみつけることや折り合いをつけることにつなげていけるとよいですね。
読んでおきたいおすすめ記事

【採用担当者向けコラム】保育士の新卒採用やることリスト。テンプレに使えるチェックシートを紹介
新卒採用は計画的に進めることが重要。保育士を目指す学生の動きは年々早期化しているとも言われるため、事前に「やることリスト」をまとめておくとスムーズです。そのうえで、早め早めに動くことが採用成功の近道で...

【採用担当必見】保育施設のお悩み対策診断。今、あなたの園に必要な対策は?
保育施設の運営にまつわる課題は、採用・定着・園児集客など、園によって本当にさまざまです。一体、自園にとって必要な対策は何なのか?「保育施設のお悩み対策診断」を使って調べてみましょう。 &n...

【採用担当者向けコラム】保育士の意向調査実施マニュアル。来年度に向けた準備のポイント
保育士さんに向けて来年度の就業意思を確認する意向調査では、どんなことに配慮して進めるとよいでしょうか。今後の園の運営や保育士さんの育成に関わることなので、慎重に行なうことが大切です。今回は、意向調査の...

【採用担当者向けコラム】意向調査で「退職希望」を示している保育士の引き止めはできる?
意向調査で退職の希望を示している保育士さんの引き止め方を知りたいと感じる採用担当者の方もいるでしょう。保育士不足が続く中、頼りにしていた保育士さんが抜けてしまうと運営が苦しくなりますよね。今回は、意向...

【2024最新】保育士不足が続く原因は?解消に向けた国・自治体・園の対策も解説
なぜ保育士不足が続くのでしょうか。子育て支援の重要性が増す中で、資格を持ちながらも保育士として就業する人が少ない状況を受け、国や自治体ではさまざまな対策を行なっています。今回は、深刻な社会問題でありな...

【2024年最新】学童保育の補助金はいくら?開業や運営に関わる助成金について
全国的に共働き家庭が増えたことで、小学生の居場所となる学童保育の拡充が求められています。実際に学童保育の開業や運営を目指す場合、国や自治体からいくらの補助金を受け取れるのでしょうか。今回は、学童保育の...

【採用担当者向けコラム】保育士の人材紹介手数料は高い?相場や会社による違いを解説!
保育士採用でも利用される「人材紹介」。手数料が何十万にも上ったという話を聞き、利用を迷っている採用担当者の方もいるかもしれません。今回は、保育士の人材紹介について、手数料の相場と費用が高いと言われる理...

【採用担当者向けコラム】真面目な人ほど急に辞めるのはなぜ?保育士が突然退職する理由と対策
真面目な人から急に辞めると告げられて、「何がよくなかったのか…」と頭を抱える採用担当者の方もいるのではないでしょうか。おとなしい人や優秀で勤勉な保育士さんほど、職場にストレスを抱えているかもしれません...

【採用担当者向けコラム】人材紹介会社が保育士さんを紹介してくれないのはなぜ?原因と対策
人材紹介会社を利用したにもかかわらず「保育士さんを紹介してくれない」と悩みを抱える方はいませんか?採用活動がスムーズに進まないと人材不足が解消されず、運営に支障をきたすケースも。今回は人材紹介会社から...

転職フェア出展は意味がない?採用できない?保育士を集客するためのポイント
多くの保育士さんと出会い、自園の魅力を直接伝えられる「転職フェア」。人材確保のチャンスになる機会ですが、出展しても意味がないのでは、採用できないのではと不安を抱く方もいるでしょう。今回は、転職フェアで...

放課後等デイサービスの職員採用の方法は?求める人材に出会うコツ
保育・福祉業界では人材不足が深刻化しており、放課後等デイサービスについても採用に苦戦する施設があるでしょう。特に児童発達支援管理責任者(児発管)の不足は、全国的に大きな課題となっています。今回は、放課...

時短勤務とは?保育園が導入するメリット・デメリットや注意点
2009年度の育児・介護休業法によって制度化された「時短勤務」。正式には短時間勤務制度と呼ばれ、3歳に満たない子を療育する労働者を対象に多くの方が利用しています。今回は時短勤務の概要や対象者、導入状況...

学童保育の経営に必要な基礎知識!開業の流れや必要コスト、成功のポイント
学童保育の開業を考えている方は、開業の流れやランニングコストの目安を把握しておくことが大切です。学童保育を経営するうえで必要な基礎知識をチェックしていきましょう。今回は、学童保育の経営に関する内容や成...

【採用担当者向けコラム】保育士採用で合同説明会に出展するメリット。成功の秘訣
保育事業者にとって合同説明会への出展には、どのようなメリットがあるのでしょうか。採用の成功率をアップするために、出展を検討する採用担当者の方もいるかもしれません。今回は保育士さん向けの合同説明会の活用...

学童保育の採用に人材紹介サービスを利用するメリットと注意点。活用するポイント
学童保育の採用に人材紹介サービスを利用するべきかと悩む事業者の方はいませんか。「手数料が高いのでは?」「希望する人材の紹介が受けられるのか」と不安を抱くこともあるでしょう。今回は、学童保育の採用に人材...

【採用担当者向けコラム】退職代行を使われた時はどうする?保育園に連絡が来た時の対処法
職員から退職代行サービスを利用して退職の申し入れがあった場合、どのように対処すればよいのでしょうか。連絡が来た時点で直接該当の職員とやり取りすることが難しいため、戸惑ってしまいますよね。今回は退職代行...

ジョハリの窓とは?4つの窓の内容や注意点、具体例をわかりやすく解説
「ジョハリの窓」という自己分析ツールはご存じですか。「開放」「秘密」「盲点」「未知」の4つの窓を用いて、自分や他者からの印象を認識していく手法です。今回は、ジョハリの窓の概要や企業内での導入時の注意点...

今、重要視される「学び直し」は保育士に必要?園側が取り組む具体例
社会人の学び直しが注目されている昨今、雇用側の環境整備が求められます。今回は、保育士の学び直しが必要なのか、園側の取り組みや具体例についてわかりやすく解説します。保育士がやりがいをもって働ける職場を作...

人的資本経営とは?保育園経営に活用するメリットや保育士育成のポイント
人的資本経営とは、企業の人材を「資本」と捉え、人材の価値を高めることで企業価値の向上を目指す経営手法です。近年注目されている経営手法のひとつで、さまざまな企業で導入されています。今回は、人的資本経営の...

学童保育を開業するために必要な資格・条件・補助金制度について徹底解説!
全国的に学童保育の拡充が求められている今、学童保育施設を開業するためには何が必要なのでしょうか。今回は学童保育の開業に必要な条件や手続き、補助金制度などを紹介します。学童保育の開業は主に自治体から業務...
- 同じカテゴリの記事一覧へ
五領域「人間関係」について理解して、保育に活かそう
今回は、保育所保育指針をもとに五領域の「人間関係」とは何か、ねらいや内容、保育園での援助のポイントを紹介しました。
五領域「人間関係」では、保育士さんとの愛着関係をベースとして、友だちと関わって遊ぶ楽しさを味わううことで、豊かな気持ちが育まれていくようです。
保育園で友だちと遊ぶうちに、自分の思いや気持ちを思い切り発揮して遊ぶことの楽しさや、自分のよさ・友だちのよさに気づいて認め合うことにつながるとよいですね。
その中で、意見や思いの食い違いに対する葛藤や試行錯誤を通して、自分の気持ちをコントロールすることやきまりの大切さを知っていけるよう援助することがポイントになります。
五領域「人間関係」について理解を深めて、毎日の保育に活かしていきましょう。
お問合せ&資料ダウンロード
採用課題・経営課題に関する個別ご相談、お問合せはこちらからお願い致します。

保育士バンク!の新着求人
お住まいの地域を選択して、最新の求人情報をチェック!






































/campaign/0004/DZ7TWBcJ3MWmgU6JV1RVa7zbReTDn5CSzSupdV30q4TVPaApz5heM6bnqp1TJkqs)