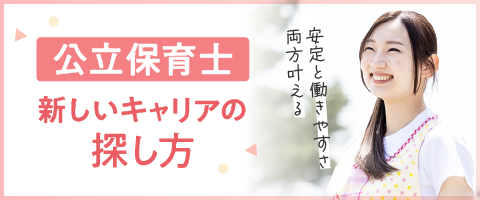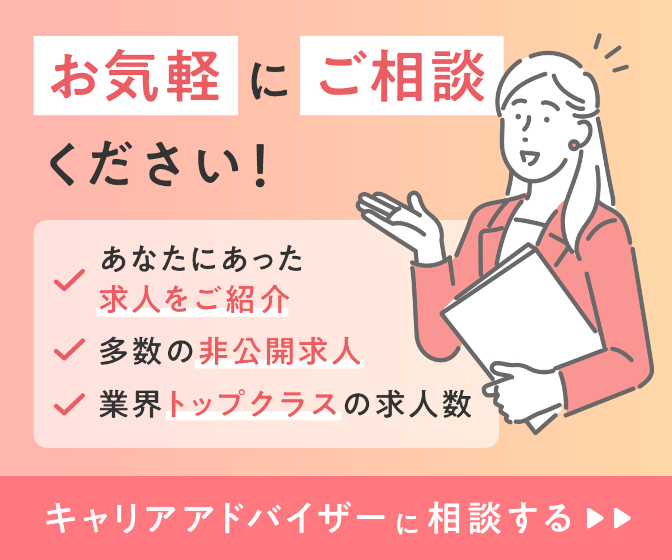子ども主体の保育が浸透してきた昨今ですが、生活発表会をはじめとする行事の取り組みではどのようなポイントを意識するとよいのでしょうか。今回、保育士バンク!では公式Instagramを通じて全国の保育士さんにアンケート調査を実施。子どもたちの主体性を育む生活発表会の取り組みに関する意見をまとめました。

生活発表会における「子どもの主体性」とは?
子どもの主体性を育むための取り組みが重要視される昨今。
そんな中、行事に関する活動において「本当に子どもが主体的に取り組めているかな?」と疑問を感じる場面もありますよね。
今回は生活発表会に着目して、行事における子どもの主体性を考えてみましょう。
行事の中で「主体性を尊重できているか」気になることがある?
公式Instagramを通じて、495名の保育士さんにアンケートを取ってみました。

8割以上の方が「はい」と答える結果に。
多くの保育士さんが、行事の進行と主体性の尊重のはざまで悩んでいることがわかります。
子ども主体の生活発表会に関する悩み
保育士さんたちは具体的にどんなポイントで悩むのでしょうか?
保育士さん
子どもの意見と言いながらも、大人の思いが先走ったり、教えやすいように誘導したりしてしまうなと感じます…。
保育士さん
行事ありきで活動が進行することに疑問を感じることがあります。
保育士さん
年長なので完成度や見栄えを求めてしまいます…。
保育士さん
いろいろな子どもの意見を聞いて内容を考えるのはすごく難しかったです。
子どもの主体的な考えを尊重しつつクラスをまとめていくというバランスが難しいことに悩みを抱えている保育士さんが多いようです。
それでは、生活発表会を子ども主体で取り組むにはどんな進め方をするとよいのでしょうか?
子どもの主体性を育む生活発表会の取り組み

tatsushi/stock.adobe.com
子どもの主体性を育む生活発表会について、保育士さんに具体的な取り組み方を聞いてみました。
導入はどのようにしている?
保育士さん
環境設定になりきり遊びコーナーを作り、子どもたちの遊び方を見守ります!
保育士さん
決まった音楽を毎日流して子どもたちの耳に自然に入るようにしていきます。
保育士さん
『子ども会議』をします!好きな絵本とかお話を出し合って決めました。先生は書記として見守るのが鉄則!
保育士さん
イメージが付きやすいように去年の映像を流していました。
保育士さん
乳児クラスなので、4月からさまざまな遊びや活動にふれて反応のよかったものを取り入れています!
普段の保育の中で徐々に浸透させるよう意識するという意見が複数寄せられました。
4~5歳児クラスなど過去に経験のある子どもたちの場合、昨年度の話をしたり映像を見せたりして話題に挙げることも多いようですね。
演目や台本はどのように決めている?
保育士さん
候補の絵本を読んでみて、一度反応を見てみます。
保育士さん
何カ月か前から絵本コーナーに物語の作品を何冊か用意して、子どもたちがよく選ぶものを見ておきます!
保育士さん
ベースとなる台本を伝えながら子どもの発想を追加していきます。
保育士さん
曲を聞いてみてどんな衣装が合うか子どもたちと話し合います!
保育士さんが複数候補を用意しておき、子どもたちの反応を見ながら決めるケースが多数のようです。
また、「発表の苦手な子、運動会で目立たなかった子が得意なことや好きな絵本から考える」という声もありました。クラスみんながどこかで輝けるように計画していきたいものですよね。
本番までの過程で意識していることは?

tatsushi/stock.adobe.com
保育士さん
「練習」という言葉は使いません!遊びの延長に発表会があるという認識で取り組みます。
保育士さん
飽きそうになったらやらないようにしています。「またやりたい」という気持ちが本番の日にピークを迎えるよう調整します!
保育士さん
ずっと遊んでいる感覚でいられるよう努めています。1回につき短時間で終わるように調整しています!
保育士さん
歌やセリフは劇以外でも話したり歌ったりして生活の中で浸透するように!無理して詰め込みすぎないよう意識しています。
子どもたちが「やらなきゃ」「覚えなきゃ」とプレッシャーを感じすぎることがないよう、遊びの延長線上で取り組むという声が。
また「間違えても大丈夫」とゆったり構えるなど、完璧を求めすぎないように心がけている先生もいましたよ。
うまく参加できない子への配慮は?
保育士さん
「その場にいればOK」として、入りたくなったら入ってもらうようにしています!
保育士さん
”その子にしかできない役”を考えるようにしています。
保育士さん
安心できる友だちと同じチームにしたり、好きな部分がある役にしたりと工夫しています。
保育士さん
無理に指導せず、褒めることを大切にしています。その子の性格に合わせて自信のつく対応を心がけています!
無理に誘うことはしないで、「見学しておいてもらう」「セリフなどを言えなくても自分の番に前に出るだけで褒める」などスモールステップで取り組むという声も届きました。
本番への意識づけはどのようにしている?
保育士さん
カレンダーにシールを貼ってカウントしています!
保育士さん
どんなところを見てほしいかイメージしてもらいます。
保育士さん
他のクラスに見てもらう機会を設けて、”お客さんに見てもらう感覚”を知らせます!
シール帳や日めくりカレンダーなどを使ってカウントダウンしていく保育士さんが多かったです。
さらに、取り組む中で子どもたちが「できたものをみんなに見てもらいたい」と自然に思えるようになる声かけをするとよいかもしれませんね。
カウントダウン日めくりカレンダーの作り方はこちらをチェック!
簡単1分登録!転職相談
保育士・幼稚園教諭・看護師・調理師など
保育関連の転職のご質問や情報収集だけでもかまいません。
まずはお気軽にご相談ください!
クラスらしさが発揮できる生活発表会にしよう
今回は、子ども主体で取り組む生活発表会の在り方について、保育士さんへのアンケート調査結果を紹介しました。
保育園の行事は、子どもの思いや考えを汲み取りながら進めていきたいもの。保育士さんたちの意見をもとに、自園の行事計画を考えてみてくださいね。
保育士バンク!ではユーザーの皆様から募集したアイデアなど、日々の保育に役立つネタを毎日配信!
さらに、今の職場に悩んでいる方向けに転職サポートも実施しています。
「相談に乗ってほしい」「近くにいい求人はある?」などの質問も受付中。お気軽にお問い合わせください!
<行事における主体性に関する調査>
調査期間:2022年10月25日~26日
調査方法:保育士バンク!公式Instagram
有効回答数:495件
<具体的な取り組み内容に関する調査>
調査期間:2022年10月27日~28日
調査方法:保育士バンク!公式Instagram
有効回答数:80件

保育士バンク!の新着求人
お住まいの地域を選択して、最新の求人情報をチェック!


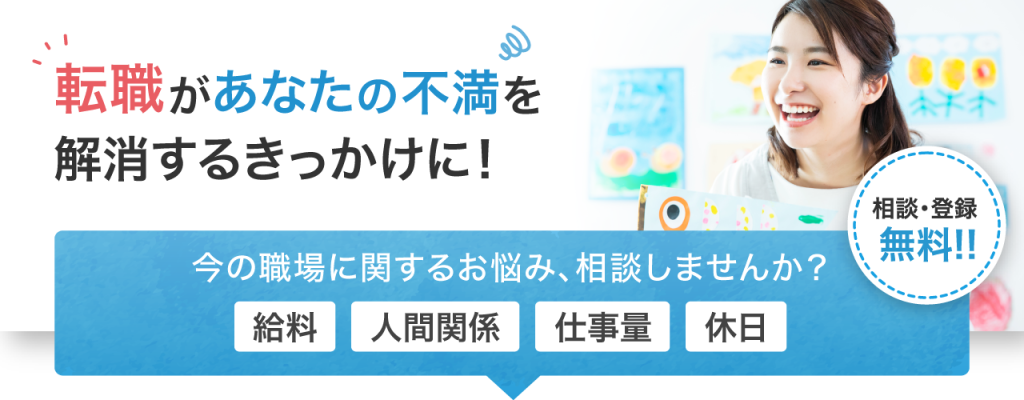





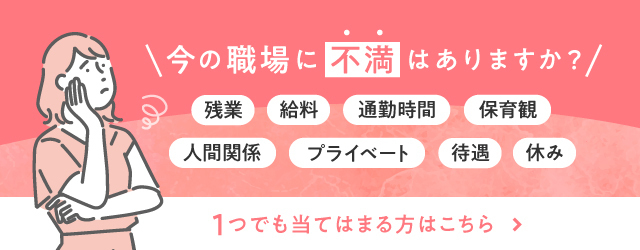
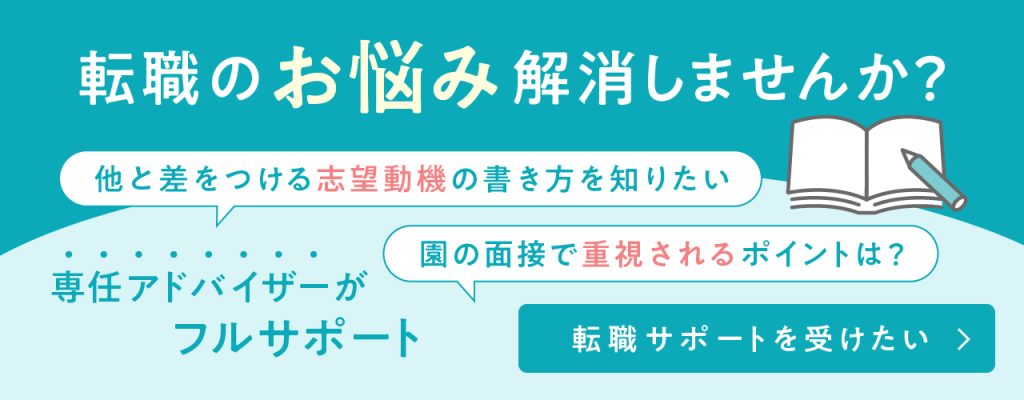
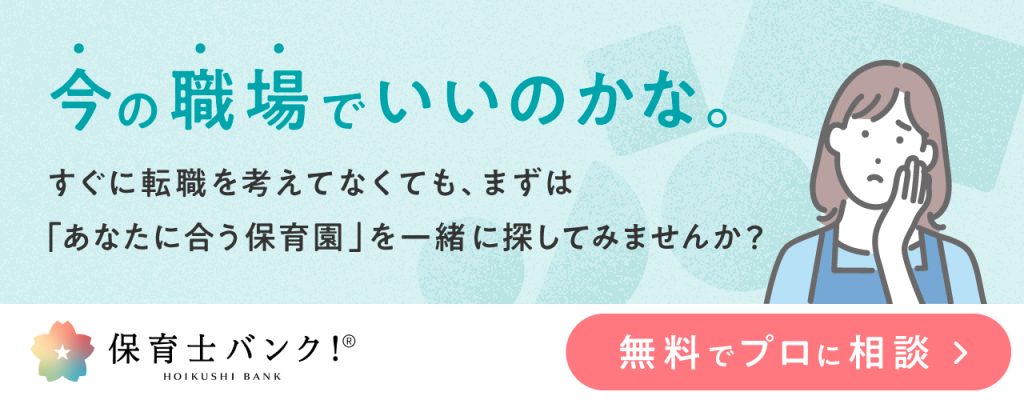
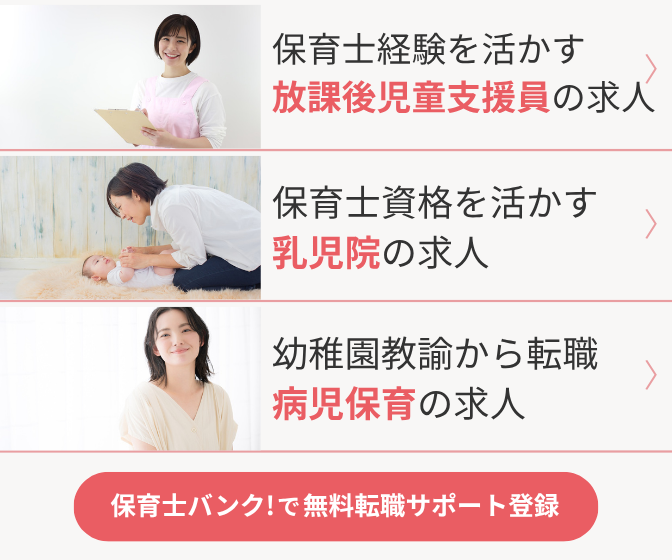



































/campaign/0004/DZ7TWBcJ3MWmgU6JV1RVa7zbReTDn5CSzSupdV30q4TVPaApz5heM6bnqp1TJkqs)