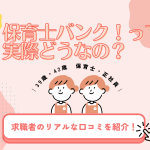事業所内保育事業とは、事業所のある企業内で、従業員の子どもや地域の子どもを受け入れて保育を行う保育所のことです。事業所内で子どもを預けることができるので、子育てをしながら働ける、という点で注目されている施設といえるでしょう。事業所内保育事業とはなにか、認可基準や補助金制度、企業主導型保育との違いなどくわしく解説します。
 milatas/shutterstock.com
milatas/shutterstock.com
目次
事業所内保育事業とは
事業所内保育事業とは、2015年4月に内閣府が施行した「子ども・子育て支援新制度」において、「地域型保育事業」の枠組みの一つとして自治体から認可を受けた認可事業です。
そもそも、地域型保育事業には、事業所内保育事業を含む4つの事業があり、事業所内保育事業のほかに、小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業が存在しています。
これらの事業は、地域ごとの多様な保育ニーズに対応し、質の高い保育を提供することにより子どもの成長を支援する目的でつくられました。
そのなかで、事業所内保育事業は、事業所内のスペースに保育施設を設置し、企業が主体となって運営することで、従業員の仕事と子育ての両立がしやすいという特徴があります。
また、従業員の子ども以外にも、保育を必要としている地域の子どもの受け入れも行っているため、待機児童問題の解消や人口減少が懸念されている地域では、子育て支援機能の維持や確保にもつながる事業といえるでしょう。
今回は、事業所保育事業に着目して、認可基準や補助金制度、企業主導型保育事業との違いなどを解説していきます。
事業所内保育事業を運営するための認可基準
はじめに、事業所内保育事業を運営するための基準について見ていきましょう。
冒頭でお話したように、事業所内保育事業は市町村から認可を受けた認可保育事業です。
そのため、事業所内保育事業を運営するためには、満たさなければいけない認可基準というものがあります。
政府の資料をもとに、事業所内保育事業の認可基についてみていきましょう。
子どもの対象年齢
事業所内保育事業で受け入れられる子どもの対象年齢は、原則として0歳児から2歳児までの子どもになります。
子どもの定員人数
子どもの定員人数は、20人以上、もしくは19人以下となっており、定員人数によって認可基準が異なります。
また、事業所内保育事業では、従業員の子どもだけでなく、保育を必要とする地域の子どもにも保育を提供するため、定員数に「従業員枠」と「地域枠」というものがあります。
地域枠については、事業所内保育事業の定員規模区分に応じて、国が定める基準を目安にしつつ、市町村の実情に応じて設定しているようです。
地域枠の例を紹介します。
定員区分:1名から10名の場合
- ・1名から5名:地域枠の定員「1名」
- ・6名、7名:地域枠の定員「2名」
- ・8名から10名:地域枠の定員「3名」
定員区分:11名から20名の場合
- ・11名から15名:地域枠の定員「4名」
- ・16名から20名:地域枠の定員「5名」
定員区分:21名から30名の場合
- ・21名から25名:地域枠の定員「6名」
- ・26名から30名:地域枠の定員「7名」
定員区分:31名から40名の場合
- ・31名から40名:地域枠の定員「10名」
定員区分:41名から50名の場合
- ・41名から50名:地域枠の定員「12名」
定員区分:51名から60名の場合
- ・51名から60名:地域枠の定員「15名」
定員区分:61名から70名の場合
- ・61名から70名:地域枠の定員「20名」
定員区分:71名以上の場合
- ・71名以上:地域枠の定員「20名」
職員の配置人数
職員の配置人数は、子どもの定員人数によって異なります。
子どもの定員人数が20人以上の場合
子どもの定員人数が20人以上の場合は、保育所と同じ配置基準となり、0歳児の子ども3人に対して保育士が1人、1歳児から2歳児の子ども6人に対して保育士が1人となります。
子どもの定員人数が19人以下の場合
定員が19人以下の場合は、子どもが0歳児の子ども3人に対して保育士が1人、1歳児から2歳児の子ども6人に対して保育士1人と、別にもう1人職員が必要となります。
必要となる資格
事業所内保育事業で働くためには、保育士資格が必要となります。
ただし、0歳児から2歳児を4名以上受け入れる場合は、保健師、看護師の資格がある方に加え、2015年4月からは准看護師の方でも、1人だけ保育士としてカウントする特例を設けています。
さらに、子どもの定員人数によって職員が必要となる資格が異なります。
子どもの定員人数が20人以上の場合
子どもの定員人数が20人以上の場合、保育所と同様とし、0歳児の子ども3人に対して保育士が1人、1歳児から2歳児の子ども6人に対して保育士が1人という配置基準となります。
このとき、職員全員が保育士資格を有しているもしくは、0歳児から2歳児を4名以上受け入れる場合は、保健師、看護師、准看護師の資格がある方を1人だけ保育士としてカウントすることができます。
子どもの定員人数が19人以下の場合
子どもの定員が19人以下の場合は、地域保育事業の枠組みの1つである小規模保育事業と同じ認可基準となります。
小規模保育事業のなかにも、A型・B型・C型の3つの認可基準があり、子どもの定員人数が19名以下の場合はA型もしくはB型の認可基準です。
<A型の場合>
事業所内保育事業の小規模保育A型の場合、保育所の配置基準である0歳児の子ども3人に対して保育士が1人、1歳児から2歳児の子ども6人に対して保育士が1人に加えて、追加の職員1人が必要となります。
追加の職員は保育士資格を有しているか、0歳児から2歳児を4名以上受け入れる場合は、保健師、看護師、准看護師の資格がある方を1人だけ保育士としてカウントすることができます。
<B型の場合>
事業所内保育事業の小規模保育B型の場合、保育所の配置基準である0歳児の子ども3人に対して保育士が1人、1歳児から2歳児の子ども6人に対して保育士が1人に加え、職員1人が追加となりますが、このとき2分の1以上が保育士資格を所有している必要があります。
先ほども説明したように、0歳児から2歳児を4名以上受け入れる場合は、保健師、看護師、准看護師の資格がある方を1人だけ保育士としてカウントすることができます。
さらに、保育士資格がない場合であっても、市町村長が行う研修を修了し、保育士もしくは保育士と同等以上の知識や経験があると市町村長から認められれば、家庭的保育補助者として働くことができます。
保育室の面積
事業所内保育事業の場合、子どもの定員人数によって保育室の面積も異なります。
子どもの定員人数20名以上
- ・0歳児と1歳児:乳児室またはほふく室を設置。乳児室は1人あたり1.65㎡、ほふく室 は1人あたり3.3㎡
- ・2歳児:保育室を設置。1人あたり1.98㎡
以上のように定められています。
加えて、給食を提供するための調理室が必要となります。
子どもの定員人数19名以下
- ・0歳児と1歳児:乳児室またはほふく室を設置。乳児室、ほふく室ともに1人あたり3.3㎡
- ・2歳児:保育室を設置。1人あたり1.98㎡
以上のように定められています。
加えて、給食を提供するため調理設備が必要となります。
保育時間
事業所内保育所の開所時間は、原則8時間となっています。
ただし、利用する従業員の勤務時間を考慮して、利用しやすい時間帯を設定している場合もあります。
このように事業所内保育所の認可基準は、自治体によって異なる場合があるようです。
出典:子ども・子育て支援新制度ハンドブックp12.p45/内閣府・文部科学省・厚生労働省
出典:事業所内保育施設設置・運営等支援助成金のご案内p4/厚生労働省
簡単1分登録!転職相談
保育士・幼稚園教諭・看護師・調理師など
保育関連の転職のご質問や情報収集だけでもかまいません。
まずはお気軽にご相談ください!
事業所内保育事業の運営支援における助成金制度
厚生労働省によると、2014年と2016年に事業所内保育事業は補助金の対象施設として、設備費や運営費、増築費等の一部が助成されていたようです。
しかし、毎年補助金制度が行われるわけではないようなので、事前に厚生労働省の資料や管轄している役所のホームページ等を確認する必要があるでしょう。
補助金制度が行われる場合、補助金を受給するためには、満たさなければいけない要件があるようです。
2016年に実施された補助金制度を参考に、くわしく見ていきましょう。
事業所内保育施設の設置費
乳幼児の定員が6人以上、かつ乳児室、保育室、調理室、便所があり、厚生労働省の規定に則った設備、構造であれば助成金が支給されます。
大企業は費用の1/2(上限1500万円)
中小企業は費用の2/3(上限2300万円)
新築、増改築の場合は建築工事費、設備工事費、外構工事費、設計監理料が対象となり、購入の場合は購入費が助成の対象です。
土地の取得にかかった費用や土地、建物の賃借にかかった費用、整地のための費用、既存の建物の解体費用、または内装の解体に要した費用、備品費は助成の対象とはなりません。
定員増などに伴う増築費(建替えを行って運営を再開した場合を含む)
5人以上定員が増える増築、もしくは5人以上の定員が増える建て替えが対象となります。
増築の場合は、大企業は費用の1/3(上限750万円)、中小企業は費用の1/2(上限1150万円)
建て替えの場合は、大企業は費用の1/3(上限1500万円)、中小企業は費用の1/2(上限2300万円)
運営費(施設の運営を開始した場合は、最初に利用を開始した日から10年間)
事業所内保育施設に配置された専任の保育士、保育従事者、看護師の給料、賞与、その他手当などが対象となります。
運営を別の企業に委託している場合は、保育士などの賃金を委託先の企業に支払った費用、もしくは委託先の企業が保育士等に支払った賃金が対象で、いずれかの低い金額のほうが支給されます。
大企業は職員1人あたり×年額34万円(上限は1360万円)
中小企業は職員1人あたり×年額45万円(上限は1800万円)
もしくは
(運営にかかった費用)-(施設定員)※最大10人×運営月数 ×大企業は月額1万円、中小企業は5000円により算出した額
以上のようになります。
このように、事業所内保育施設の補助金制度が実施される場合は、満たさなければいけない要件があるので注意するようにしましょう。
出典:[平成28年度版] 事業所内保育施設設置・運営等支援助成金のご案内p4~p7/厚生労働省
事業所内保育事業と企業主導型保育事業との違い
 maroke/shutterstock.com
maroke/shutterstock.com
ここまで、事業所内保育事業について解説してきましたが、事業所内保育事業と似た「企業主導型保育事業」があります。
企業主導型保育事業とは、2016年度に内閣府が企業向けに提案した制度で、事業所内保育事業を主幹とし、保育サービスの拡大と待機児童の解消を図ることを目的としてつくられました。
さらに、従業員の働き方に応じて柔軟に対応できるので、仕事と子育てを両立しやすいという特徴もあるため、事業所内保育事業と何が違うのか気になりますよね。
企業主導型保育事業と事業所内保育事業には、どのような違いがあるのかみていきましょう。
認可の違い
事業所内保育事業と企業主導型保育事業では、認可の有無に違いがあります。
そもそも、保育施設には認可保育施設と認可外保育施設がありますよね。
冒頭で説明したように、事業所内保育事業は自治体の認可を得た上で開設するため、施設区分としては認可保育施設になります。
一方、企業主導型保育事業は、自治体から認可を受けていないため、認可外保育施設になります。
子どもの対象年齢
事業所内保育事業は原則0歳児から2歳児までですが、企業主導型保育事業では年齢制限はなく、0歳児から小学校就学前の子どもとなります。
子どもの定員人数
事業所内保育事業と企業主導型保育事では、子どもの定員人数における「地域枠」の範囲に違いがあります。
事業所内保育事業
事業所内保育事業においての「地域枠」は、事業所内保育所全体の定員規模区分に応じて、国の定める基準を目安にしながら、自治体が地域の状況に合わせて設定します。
企業主導型保育事業
企業主導型保育事業の場合、企業で働く従業員の子どもの保育のみで運営することができます。
ただしその中で、全体定員数の2分の1以内であれば、「地域枠」として地域内の子どもたちが利用できるような設定も可能なため、事業所内保育事業よりも地域枠の定員人数は広いと言えそうです。
保育士の配置基準
事業所内保育事業と地域型保育授業は、職員の配置人数にも違いがあります。
事業所内保育事業の場合は、子どもの定員人数が20人以上の場合は、0歳児の子ども3人に対して保育士が1人、1歳児から2歳児の子ども6人に対して保育士が1人と、保育所と同じ配置基になります。
また、子どもの定員人数が19人以下の場合は、0歳児の子ども3人に対して保育士が1人、1歳児から2歳児の子ども6人に対して保育士が1人と、保育所の配置基準に加えてもう1人職員が必要となります。
一方、企業主導型保育事業の職員の配置基準は、0歳児の子ども3人につき保育士1人、1歳児から2歳児の子ども6人につき保育士1人、3歳児の子ども20人につき保育士1人、4歳児から5歳児の子ども30人につき保育士1人、それに加えて職員をもう1人配置することとし、最低2人を下回ることはできません。
補助金制度
事業所内保育事業の場合、自治体から認可を受けた認可保育施設のため設備費や運営費、増築費などが助成される、補助金の対象施設となります。
ただし、受給する要件を満たす必要があるため、確認する必要があるでしょう。
一方、企業主導型保育事業は、認可外保育施設ではあるものの、認可保育施設と同等の補助金を受けることができます。
運営費であれば、子ども・子育て支援新制度における、小規模保育事業などの公定価格と同水準、整備費は認可保育所の施設整備と同水準の補助金が交付されますが、運営の規模によっては支給される額が異なるようです。
出典:1. 企業主導型保育事業の制度の概要と企業のメリット/内閣府
出典:子ども・子育て支援新制度ハンドブックp3.p12.p45/内閣府・文部科学省・厚生労働省
出典:仕事・子育て両立支援事業の概要 (企業主導型保育事業)p9.p13.p16/内閣府
読んでおきたいおすすめ記事

保育士資格やスキルを活かしてデスクワークがしたい!仕事の種類やメリット
保育士さんは、デスクワークで働くことができるのでしょうか。保育士資格やこれまでのスキルを活かせるような職場があるのかも気になりますよね。今回は、保育士さんが働けるデスクワークの仕事にはどのようなところ...

乳児院で働くには?必要な資格や仕事の魅力、給料などを徹底解説
乳児院で働くには、必要な資格や仕事内容、給料などを把握することが大切です。1日の流れや求人の探し方などを知り、転職活動の参考にしてみてくださいね。今回は、乳児院について徹底解説します。乳児院の仕事の魅...

在宅ワークで保育士資格を活かせる仕事とは?自宅でできる保育関係の仕事を徹底解説
通勤時間なく働ける在宅ワークをしたいと考えても「保育士は無理なんじゃないか……」とあきらめている方はいませんか?保育園の事務職や保育ママ、保育園業務のサポートなど、保育士の経験や資格を活かして自宅でで...

保育園運営会社の仕事内容とは?本社勤務でも保育士資格は必要?働くメリットや求人事情まで
保育園運営会社にはどんな仕事があるのでしょうか?保育園運営会社で働くことは「本社勤務」とも呼ばれ、保育園の運営に携わる仕事として、主に一般企業に就職したい保育士さんにとって人気の高い職種のようです。今...

子どもと赤ちゃんに関わる仕事31選!必要な資格や保育士以外の異業種、子ども関係の仕事の魅力
子どもや赤ちゃんと関わる仕事というと保育士や幼稚園の先生を思い浮かべますが、子どもに関係する仕事は意外とたくさんあります!今回は赤ちゃんや子どもと関わる仕事31選をご紹介します。職種によって対応する子...

企業内保育所とはどんな施設?保育士として働くメリットや仕事内容、転職先の選び方
企業内や企業に併設された企業内保育所とは、どんな保育所なのでしょうか。仕事内容などを知りたい保育士さんは多いようです、今回は、少人数制でアットホームな環境で保育ができる施設が多い企業内保育所について、...

保育士が保育に集中できる職場「託児所」の特徴や仕事内容とは?
託児所とは子どもを預かる施設を指しますが、保育園や国の一時保育とどのような点が違うのでしょうか。託児所は夜間保育や短時間の預かりなどの保護者の多様なニーズに対して柔軟に応えられるため、需要の増加が予想...

保育士をサポート・支える仕事特集!異業種への転職も含めた多様な選択肢
保育士の経験を経て、これからは保育士のサポート役として働きたいという方はいませんか?責任の重い仕事だからこそ、人の優しさや支えが必要不可欠な仕事かもしれませんね。今回は、保育士さんをサポートする・支え...

保育士を辞める!次の仕事は?キャリアを活かせるおすすめ転職先7選!転職事例も紹介
保育士を辞めたあとに次の仕事を探している方に向けて、資格や経験を活かせる仕事を紹介します。ベビーシッターなど子どもと関わる仕事はもちろん、一般企業での事務職や保育園運営会社での本社勤務といった道も選べ...

病院内保育とは?働くメリットや1日のスケジュール、一般的な保育施設との違いについて紹介!
病院内保育とは、病院や医療施設の中、または隣接する場所に設置されている保育園のことです。保育園の形態のひとつであり、省略して院内保育と呼ばれることもあります。転職を考えている保育士さんの中には、病院内...

フリーランス保育士として自分らしく働くには。働き方、収入、仕事内容からメリットまで解説
保育園から独立して働くフリーランス保育士。具体的な仕事内容や働き方、給料などが気になりますよね。今回は、特定の保育施設に勤めずに働く「フリーランス保育士」についてくわしく紹介します。あわせて、フリーラ...

保育園の調理補助に向いてる人の特徴とは?仕事内容ややりがい・大変なこと
保育園で働く調理補助にはどのような人が向いてるのでしょうか。子どもや料理が好きなど、求められる素質を押さえて自己PRなどに活かしましょう。また、働くうえでのやりがいや大変なことなども知って、仕事への理...

子どもと関わる看護師の仕事10選!保育園など病院以外で働く場所も紹介
子どもに関わる仕事がしたいと就職・転職先を探す看護師さんはいませんか?「小児科の経験を活かして保育園に転職した」「看護師の資格を活用してベビーシッターをしている」など保育現場で活躍している方はたくさん...

保育士から転職!おすすめの異業種22選≪あなたの資格・経験を活かせる次の仕事とは?≫
保育士以外から異業種への転職を考えている際、どのような転職先がおすすめなのでしょうか。今回は、次の仕事として保育士から転職しやすいおすすめの異業種22選を紹介します。保育士から異業種に転職するメリット...

【保育士の意外な職場10選】こんなにあった!保育園以外の活躍できる場所
保育士の経験やスキルが、実は意外な職場で活かすことができるのを知っていますか?転職を検討しつつも、子どもとかかわりたい、資格や経験を活かしたいと考えている人は多くいるでしょう。保育園や幼稚園以外で保育...

【完全版】保育士資格を活かせる仕事・働ける企業25選!
保育士資格を持っていたら、保育園で保育士として働くのが当たり前だと思っていませんか? 実は現役の保育士さんの転職先としては、保育園や幼稚園などの保育現場以外にも一般企業や福祉施設、ベビーシッターなど、...

【2024年最新】保育士に人気の転職先ランキング!異業種や選ばれる職場を一挙公開
保育士の資格を活かして働ける人気の転職先をランキング形式で紹介!企業主導型保育園や病院内保育所、ベビーシッターなど保育士経験やスキルを活かせる職場はたくさんあります!今回は保育施設や異業種別に詳しく紹...

【2024年最新版】幼稚園教諭免許は更新が必要?廃止の手続きや期限、対象者をわかりやすく解説
幼稚園教諭免許は更新が必要なのか、費用や手続き方法などを知りたい方もいるでしょう。今回は、2022年7月1日より廃止された教員免許更新制について詳しく、そしてわかりやすく紹介します。幼稚園教諭免許を更...

保育士が児童発達支援管理責任者(児発管)になるには?実務経験や要件など
保育士の実務経験を活用して目指すことができる「児童発達支援管理責任者(児発管)」は、多くの障がい児施設で人材不足の状況が続いています。今回は保育士が児童発達支援管理責任者(児発管)になるための方法を徹...

保育士は年度途中に退職してもいいの?理由の伝え方や挨拶例、再就職への影響
「年度途中で退職したい...けれど勇気が出ない」と悩む保育士さんはいませんか。クラス担任だったり、人手不足だったりすると、退職していいのか躊躇してしまうこともありますよね。そもそも年度途中で辞めるのは...

幼稚園教諭からの転職先特集!資格を活かせる魅力的な仕事18選
仕事量の多さや継続して働くことへの不安などを抱え、幼稚園教諭としての働き方を見直す方はいませんか。幼稚園教諭の転職を検討中の方に向けて、経験やスキルを活かせる18の職場を紹介します。保育系の仕事から一...

【2024年度】放課後児童支援員の給料はいくら?年代別の年収やこの先給与は上がるのかを解説
放課後児童クラブや児童館などで働く「放課後児童支援員」の平均給料はいくらなのでしょうか。別名「学童支援員」とも呼ばれ、「給与が低い」というイメージがあるようですが、国からの処遇改善制度などにより、これ...

保育士が働ける保育士以外の仕事21選。資格や経験を活かせるおすすめの就職先
保育園以外の職場に転職・就職先を探す保育士さんもいるでしょう。今回は企業内保育所や託児施設、児童福祉施設など、保育士さんが働ける保育園以外の職場を21施設紹介!自身の働き方や保育観を見つめ直し、勤務先...

【2024年最新】保育士の給料は上がる?いつから?9000円賃上げの処遇改善によって数万円の加算も期待
保育士の給料が上がる国の施策として、2022年2月からの「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業(保育士の処遇改善Ⅲ)」で、2年にわたり月9000円の賃上げが行なわれました。また勤続年数などで加算さ...

私って保育士に向いていないかも。そう感じる人の7つの特徴や性格、自信を取り戻す方法
せっかく保育士になったのに「この仕事に向いていないのでは?」と不安を抱いてしまう方は多いようです。子どもにイライラしたり、同僚や保護者と上手くコミュニケーションが取れなかったりすると、仕事に自信が持て...

ベビーシッターとして登録するなら「キズナシッター」を選びたい理由トップ5
ベビーシッターとしてマッチングサービスに登録する際に、サイト選びに悩んでいる方も多いのではないでしょうか。収入や働き方の安定性、サービスごとの特徴や魅力も気になりますよね。本記事ではそんななか「キズナ...

子育て支援センターとは?保育士の役割や必要な資格をわかりやすく解説!
子育て支援センターとは、育児中の保護者と子どもをサポートする地域交流の場です。保育士経験者は資格を活かして働けるため、転職を考える方も多いよう。また、子育て経験を活かして相談員として勤務したい方もいる...

ベビーシッターになるには?資格や仕事内容、向いている人の特徴
ベビーシッターになるにはどうすればいいのでしょうか?まずは必要な資格やスキルをチェックしましょう。ベビーシッターは働く時間や場所を柔軟に調整できる場合が多く、副業としても人気です!初めてでも安心してベ...

【2024年最新版】子育て支援員とは?資格の取り方・研修、やりがいや仕事内容について解説
保育の仕事に興味がある方のなかには、子育て支援員とはどんな資格?と気になっている方がいるかもしれません。2023年に新設されたこども家庭庁が、放課後児童クラブ(学童保育)の人材確保に取り組んでいるなか...

保育士の転職の時期はいつが最適?後悔しないタイミング&スケジュールの立て方
保育士の転職の最適な時期とはいつなのでしょうか?スムーズに内定を獲得できるよう、いつから動き始めればよいのかなど、転職活動における適切なタイミングを知っておきましょう。今回は、保育士さんの転職に最適な...

【2024年版】幼稚園教諭免許の更新をしていない!期限切れや休眠状態の対応、窓口などを紹介
所有する幼稚園教諭免許が期限切れになった場合の手続きの方法を知りたい方もいるでしょう。更新制の廃止も話題となりましたが、更新していない方は今後の対応方法をくわしく把握しておくことが大切です。今回は、幼...

【2024年最新】調理師の給料、年収はどれくらい?仕事内容や求人、志望動機なども徹底解説
保育園の調理師は、子どもたちが毎日口にする給食やおやつを作る仕事です。成長する子どもの身体づくりを助ける存在として、やりがいをもって働けるかもしれません。しかし、年収はどれくらいなのでしょうか?今回は...

インターナショナルスクールに就職したい保育士さん必見!給料や仕事内容、有利な資格とは
保育士さんが活躍できる場所のひとつとしてインターナショナルスクールがあります。転職を検討するなかで、英語力は必須なのか、どんな資格が必要なのかなどが気になるかもしれません。今回は、インターナショナルス...

児童館職員になるには?必要な資格や仕事内容、給料
児童館は、地域の子どもたちへの健全な遊び場の提供や子育て家庭の育児相談などを行なう重要な施設です。そんな児童館の職員になるにはどのような資格が必要なのかを解説します。また、児童館の先生の仕事内容や20...

病児保育とはどのような仕事?主な仕事内容や給与事情、働くメリットも解説
病児保育とは、保護者の代わりに病気の子どもを預かる保育サービスのことを言います。一般的に、風邪による発熱などで保育施設や学校に通えない子どもを持つ保護者が利用します。今回は、そんな病児保育の概要を詳し...

保育士の給料・年収は?安いのはなぜ⁉年齢・地域別・パートの平均年収、給与UP術
「給料が安い」「上がらない」といわれる保育士の給料はいくらくらいなのでしょうか。子どものお世話や保護者対応など多くの仕事をこなす中で給与が低いと不満が募りますよね。今回は保育士の月給や平均年収を徹底解...

保育園事務は何がきつい?仕事内容や給料、業務で楽しいことについても紹介
子どもたちが通園する保育園で事務として働く場合の仕事内容とはどのようなものが挙げられるのでしょうか。中には、仕事に就いてから「きつい」「つらい」と感じることもあるかもしれません。今回は、保育園事務の仕...
- 同じカテゴリの記事一覧へ
事業所内保育事業の特徴を知って地域の保育ニーズに対応しよう
事業所内保育事業は、事業所のある企業内で、従業員の子どもや地域の子どもに保育を提供することができる認可保育事業です。
待機児童問題の解消を目的としてつくられた事業の一つでもあるため、仕事と子育てを両立したい方にはとても助かりますよね。
事業所内保育事業は市区町村の認可を受けた認可保育施設のため、補助金の対象施設でもあります。
しかし、補助金制度を受けるためには満たさなければいけない要件があったり、実施されているかを確認する必要があるので注意が必要です。
地域の保育ニーズに柔軟に対応できる事業所内保育事業についてきちんと理解して、活用するようにしましょう。

保育士バンク!の新着求人
お住まいの地域を選択して、最新の求人情報をチェック!
























/campaign/0004/DZ7TWBcJ3MWmgU6JV1RVa7zbReTDn5CSzSupdV30q4TVPaApz5heM6bnqp1TJkqs)