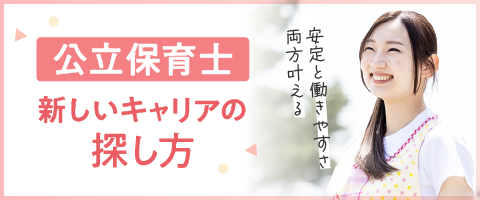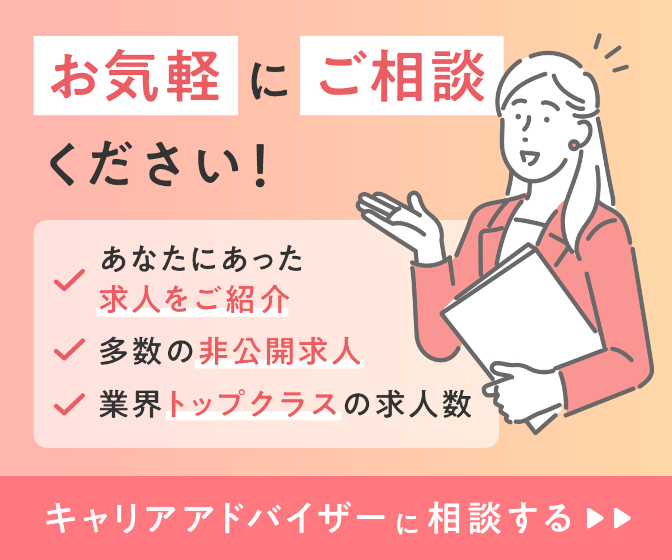未来を生きる子どもたちにいま、そしてこれから保育者ができることは何か。
保育教育研究の第一線に立つ研究者の方々にきく、保育士バンク!連載企画第1回。『いま大きく変わる保育の質』について汐見稔幸教授にインタビュー。前編は『子どものためにいまできる保育』について、エピソードとともに保育者が子どもの育ちとどうかかわっていくのか、丁寧に迫っていく。

2018年。10年に一度の保育所保育指針の改定が行われた。厚生労働省が編集した解説書は、改定前ものと比較すると、厚みは約1.75倍に及ぶ。
3法令(保育所保育指針、幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領)の同時改定。そして2020年から始まる教育改革。
いま、保育・幼児教育の何が大きく変わろうとしているのだろうか。
今回は、保育所保育指針改定をとりまとめた白梅大学名誉教授、汐見稔幸先生にインタビュー。保育の質を向上させていくために、保育者がいまできることとは何か、汐見稔幸先生が考える、保育者の仕事の意味とは。
取材で訪れたのは、東京都内とは思えぬほど豊かな緑に囲まれた、汐見先生のご自宅.。事務所がご自宅だとは知らず、玄関先で戸惑っていると、「こっちこっち。入っておいで」 と、家の中から優しい声が。
声をたどって家に上がると、さまざまな書物がうず高く積み上げられた本の山の中から、汐見先生がひょっこりと顔を見せてくれました。
【1】保育者の仕事とは『人間の幸せ』を考えること
保育者の仕事の意味
ーーー2018年の改定で、保育所保育指針が大きく変わったと感じています。
毎日子どもと向き合う保育者の仕事は、いままでと何が変わるのでしょうか
これからは、あらゆるのものに人口知能が組み込まれ、人間が苦労してやってきたことの大部分を機械が行う『AI社会』になっていくでしょう。生活スタイルも価値観も変わる。 変化がめまぐるしい時代を幸せに生きるためには、どんな力が子どもたちには必要か。 そもそも、幸せとは何か。
それを考え続けるのが、これからの保育者の仕事なんです。

でも実は、どんなに文明が進歩しても、人間が「本当に生きていてよかった」「幸せだ」と思うことは、何十万年経ったいまでも変わっていないんですよ。
というのも、長い人類の歴史の中で、人間はずっと『3つのこと』を大事にして、生活してきたからです。
人間が大事にしてきた「3つのこと」
1つ目は、体で覚えていくこと。
体で技を覚えて、さらに技の水準を上げて上手になっていくこと。それはつまり『成長』です。
人間は先祖が編み出してきた技や文化を受け継ぎ、体に刻み覚えさせていった。
ピアノが弾けるようになる、サッカーができるようになる、絵を描いて表現できる。
そして周りに認められる経験を積むことで、さらに上手になる。それは人間にとっての『生きがい』になります。
2つ目は、とにかくみんなで考え、議論すること。
「どうしよう」と自分で考え、「こうしよう」とみんなで話し合い、実行し「できたー!」と進歩する。そうやって人は文明を築いてきたでしょう?
考え抜いた結果、パッとアイデアが思い浮かぶ。人間にとって一番『楽しい』瞬間といえます。
3つ目は、他者と豊かに関わること。
親子、夫婦、恋人、同僚、コミュニティ。
さまざまな関係性がありますが、人間はお互いの心が理解できているときは、すごく幸せを感じるんです。
でも失恋やケンカのように、相手に理解してもらえないと感じたり、少しでも関係性が上手くいかなくなると、苦しさを感じる。
だから、人間関係を上手に作っていくために、いろいろな人とどれだけ豊かに共感できる人間になるかが大事になる。
つまり人間にとっての幸せとは、『豊かな人間関係を作れるかどうか』なんです。
AI社会を幸せに生きるための力
ーーー確かに、成長することやアイデアを出し合うこと、豊かな人間関係を築くことは、どんな時代でも、きっと変わらず幸せを感じられることですね。
でもいま、人類がずっと大事にしてきたこの3つを『鍛える場』が、生活の中からどんどん減っている。
未来のAI社会では、体を動かさなくても、考えなくても、スイッチを押せばすべてが完了する。なんでも簡単にできてしまうから、体で生きがいを感じられないですよね。
では、人間はどうすれば幸せでいられるのか。
『体で覚えていくこと』『アイデアを出し合うこと』『豊かな人間関係を作ること』。 機械ができないこの3つのことを、面白がって生活できる人間が、幸せに生きられるんじゃないかな。
生きるための最低限の仕事は機械に任せて、人間はその上を楽しむ。
物事を面白がる力がないと、人間はAI社会に支配されてしまうでしょう。
『幸せを自分で探し出す子ども』を育てる

ーーーずっと大事にしてきた3つのことを鍛える場が減ってきているいま、保育者として何をすべきなのでしょうか。
保育者は、3つの大事なことを子どもたちが大好きになるように、保育をするのです。
実は、3つの大事なことを育てる取り組みは、いままでの保育・幼児教育でかなりやっています。
いままでのやり方を急に変えたいわけではないし、特に難しい保育をしよう、というわけではないんです。
でもこれからは『育てる』というより、子どもが3つのことを『大好き』になるように保育をしてほしい。『大好き』になるためには、子ども自身が「やりたい!」と思って、自発的に行動したり、工夫することが大事になります。
【2】子どもの『やりたい!』を引き出す環境作り
子どものレベルに合わせた環境を作る
ーーー子どもたちが自発的に行動したり工夫するために、保育者は、どのようなスタンスで幼児教育・保育を行っていけばいいのでしょうか。
保育者は、『子どもは教育されるから育つのではなく、自分で自分を育てようとする力をもっている』ことを知っておいてほしい。
現代においては、技術の発達により、最新の測定器が開発され、赤ちゃんの行動から脳のどの部分が働いて、何を考えているかなど、以前よりも分析したり研究できるようになりました。
例えば、いままで赤ちゃんは目が見えないとされてきましたが、焦点を絞るのがまだ難しい段階なだけで、いまではだいたい0.01くらいの視力があることがわかっています。
いま、ロボット学、小児科医、心理学者、さまざまな分野の研究者たちが赤ちゃんの研究を進める中で、共通して認識していることは『赤ちゃんは教育されるから育つのではなく、自分で自分を育てようとするから育つ』ということです。
つまり人間は、人に教えられ指示通りできたからといって、伸びるわけではないんです。
 buritora/shutterstock.com
buritora/shutterstock.com
ーーー「自分で自分を育てようとする」とは、子どもたちのどのような姿や行動からわかるのでしょうか。
子どもは、自分のレベルの少し上の力が必要だとわかると、自分で挑んでいくんです。 例えば、10の力がある子どもが、周りを見て「あれ面白い!」と思う。
そして、「あの面白いことをやるためには、11か12の力が必要なんだな」とわかったら、自発的にやっていきます。ところが、20の力が必要だと思うとやらないんですよね。
ーーー「面白そう!」「あれならちょっと頑張ればすぐにできそう!」と思うことが、自発性を刺激するきっかけなんですね。
そうですね。
でも一方で、『何が面白いか』は子どもたちが自分のレベルに合わせて考えるから、保育者が全部設定できないんですよ。
だから子どもたち全員が一斉に同じことをするのではなく、自分のレベルに合ったやりたい活動ができる空間を作っておくのが大切なんです。
遊び道具がいっぱいある空間、本を読みたい子のための本が読める場所、サッカーをやりたい子のための外で自由に遊べる場所。
そんな環境を作ると、子どもは勝手に動き出して、不思議なことに、いまよりもうちょっと上のレベルに行きたいと思う。
必ず上のレベルに行きたがるっていうのは、人間の本能かもしれないですね。
子どもを観察し、遊びの先を予測する
ーーー子どもが少し上のレベルに行きたいと思う環境を作るために、保育者はどのようなことを意識すればいいのでしょうか。
子どもがもっと伸びたい、もっとできるようになりたいと思う環境を作るには、保育者が常に子どもを観察して、『あの子は次はあれをやりだすんじゃないかな』と予測していくことが求められます。
例えば、いまクラスで『結ぶ』ことが流行っているとする。
「“結ぶ”を発展させて何か面白い遊びってないかしら」と連想してみましょう。
「ひもをいっぱい置いておいたら気づくかな?」
「いろいろな色のひもだったら興味を持つかな?」
というふうに、環境をいろいろ工夫する。
ようやく子どもが「色がついているひも、きれい!」と興味を持ち始める。 そこで保育者が「この紐とこの紐を結んでみようか」なんて言ったら、遊び出したりする。
でも先を予測して環境を作っても、その通りに子どもがするとは限らない。
そのあたりは、保育者としての経験が必要な部分もあるでしょう。
とにかくいろんな工夫をしてみよう、ということなんです。
もちろん「こういうふうにしたら面白いよ」と言ってもいい。
でも子どもは興味がなかったら乗ってこない。
乗ってくるんだったら、興味があるってことになる。
子どもの『心』に応答する
ーーー保育者は子どもの遊びの先を予測して、環境を作り、観察しながら見守っていくのですね。
でも保育者っていうのは、単に見守っていればいいわけではないんですよ。
見守りながら、
「この子は次に何をやりたがるのか」
「この遊びをして、どんなふうに育っているのか」
「この子はいま、こういう力を身につけたがっているのだから、全く別のことを始めるかもしれない」
というふうに、子どもの心の中で育ってるものや、次に芽生えている関心などを読み取る能力を、保育者も常に訓練して環境作りをする。
これが『応答する』ということです。
 MIA Studio/shutterstock.com
MIA Studio/shutterstock.com
子どもが遊びで行き詰っていることもある。
子どもは、自分の力を伸ばそうとしているんだけど、自分だけでは十分にできないことはたくさんあって、途中で投げ出してしまう場合もあるでしょう。
そういうときは、
「ちょっと手伝ってあげようか」と声をかけてみよう。
ほんの少し手助けしてあげれば、また急にやりだすときもある。
もちろん黙っているだけのほうがいいときもあります。子どもがイライラしているときとかね。
でも、本当に何もやらないときは、興味をもたせるために「先生遊んでみようかな~」なんて言いながら、スッとモデルを見せてあげましょう。
このあたりも、保育者としての経験が必要な部分でもあります。
同じ遊びをやりこめる環境も大事
ーーー子どもの『心』に応答するとありましたが、子どもの興味は日々移り変わると思います。毎日変わる興味に合わせて、環境は変えていくべきなのでしょうか。
全然違うことばかりやってしまうと、子どもにとって育ちにくい力もあるでしょう。 ひとつの遊びを続けてレベルを上げていく、そのための環境を保育者が作ることもできます。
例えば最近、毎日のように紙飛行機飛ばしをやり続けている子どもたちがいる。
そこで保育者は、
「誰よりもよく飛ぶ飛行機を作りたい!」
「もっとかっこいい飛び方をする飛行機は作れないかな?」
「長く飛ばし続けるにはどうしたらいいんだろう?」
と子どもたちの中で紙飛行機への興味がさらに高まっていくだろうと予測する。
だったら、明日は『紙飛行機の作り方』という本を机に置いておこうか。いろんな厚さの紙を用意しておこうか。
子どもたちは、保育者が設定した紙飛行機作りを思う存分やりこめる環境で、自分なりの紙飛行機を試行錯誤ながら作っていくのです。
そうやって、毎日いろいろやってるけど、ひとつ同じ遊びや活動を続けてレベルを上げていく。
そのための環境を作るということも大事なんですよ。
遊びを途切れさせない工夫
 ANURAK PONGPATIMET/shutterstock.com
ANURAK PONGPATIMET/shutterstock.com
ーーー遊びを毎日続けて、もっと深めていきたい。しかしいまの保育園や幼稚園だと、お片づけの時間があり、遊びが途切れてしまう場合もあると思います。解決策として、いいアイデアはありませんか?
「遊びの続きをやりたい」という子どものために、「翌日に続きから始めればいいんだよ」という連続性を保証するには、ちょっとした工夫が必要です。
特に保育園では、ひとつの部屋を食事に使ったり、午睡をしたりするのに使うから、確かに難しいこともあるよね。
ある保育園では、“輪っか”を利用しています。
子どもたちが午睡の前に積み木でお城を作った。明日は続きをするんだ、という子どものために、「これは壊さないで」とわかるよう、積み木を“輪っか”で囲んでおく。
そうしておけば、次の日はそこから始められる。子どもが「やっぱり今日はもういいや」となったら、輪っかを外せばいい。
遊びを途切れさせない工夫をしている幼稚園や保育園は、たくさんあります。
簡単1分登録!転職相談
保育士・幼稚園教諭・看護師・調理師など
保育関連の転職のご質問や情報収集だけでもかまいません。
まずはお気軽にご相談ください!
【3】『3つの大好き』を育てるための手掛かり

ーーー子どもたちに3つのことを大好きになってもらうためには、一人ひとりに寄り添った環境作りが大切ですが、同時にその難しさも感じます。日々の保育で何か手掛かりになるものはないでしょうか。
これからの保育は、設定した環境で子どもたちが本当に遊んでいるのか、『観察』し『記録』することがとても大事になってきます。
しかし、毎日たくさんの子どもが、いろいろな場所でさまざまな遊びをしていたら、詳細なことや大事なことは、見逃してしまったりすぐに忘れてしまうでしょう。
いままで通りの記録の方法では、『遊びの記録』がまったく何も残っていないということが起こりうる。それじゃあ困ってしまう。
そんなことがないように「デジカメとICレコーダーもって保育しよう」って僕は提案しているんです。
筆記スタイルにこだわる必要はないんです。
つまり、子ども一人ひとりに寄り添った、遊び中心の保育にするためには、いまの記録のやり方を全く変えていかないといけないんだよね。
「あ、これいいシーン」カシャ!
「あ、これ次に活かせそう」カシャ!
というふうにどんどん撮る。
子どもが午睡している間に、撮った写真をぱぱぱぱっと貼り付けて、一斉に並べながら「これは何時ごろで、これはこの場面」というふうに思い出す。子どもたちが1日の中でどんなことで遊んで、どんなことに興味を持ったか記録していくのです。
観察や記録をに基づいて、環境作りを評価しやり直していく。そういったサイクルが保育者の経験になっていく。
だから、もっとデジカメやICレコーダーなどを有効に活用して、子どもたちの記録を作っていきたいですね。
保育士・幼稚園教諭・看護師・調理師 etc.無料転職サポートに登録
【4】保育者は難しい。だから最高に面白い

ーーー保育者の仕事とは、人間の幸せについて考えること。子どもたちが「面白い」「幸せだ」と思うことを、自分自身で見つけられる力を育てるために、保育者自身が多くの経験をし、保育の質を磨いていく必要があるのですね。
だから、保育者というのは一人前にできるようになるまで、随分時間がかかりますよ。
決められた教材が用意されていて、保育者は教え方を練習する、というような明確な指導法がないんです。
『子ども』という人間の気持ちをしっかり読み取り、次にやりたくなるのは何かを予測していろいろな環境を作っていかないといけない。
同じことをAちゃんにやったらすごくノッてきた、Bちゃんにやったらまったくノラない。保育では、しょっちゅうあることじゃないですか?
こんなにも難しい仕事はないかもしれない。
だからこそ、ある意味、保育者が一番人間をよくわかっているよね。 そうならざるを得ないくらい難しいけれど、面白い仕事でもあるのです。
【前編・終】
保育者の仕事の本質と、保育者自身が保育の質を磨いていく大切さや楽しさについて伺いました。
では、いままでの日本の保育や幼児教育は、どうだったのでしょうか。このタイミングで「保育の質」を大きく変える、その背景とは?
子どもの育ちをめぐる環境は、昔といまではどう変わっているのか、汐見先生のお話は中編に続きます。
読んでおきたいおすすめ記事

【2026年版】乳児院で働くには?必要資格と給料、保育園との違いを解説
「乳児院で働くにはどうすればいいの?」と考える保育士さん必見!乳児院は、さまざまな事情で家庭で暮らせない0歳児~2歳頃の子どもを24時間体制で養育する施設です。保育士の方は仕事内容や保育園との違いなど...

子どもと関わる仕事31選!必要な資格や保育士以外の異業種、赤ちゃんや子ども関係の仕事の魅力
子どもや赤ちゃんと関わる仕事というと保育士や幼稚園の先生を思い浮かべますが、子どもに関係する仕事は意外とたくさんあります!今回は赤ちゃんや子どもと関わる仕事31選をご紹介します。職種によって対応する子...

企業内保育所とは?持ち帰り仕事ゼロの理由と仕事内容のリアル!給料や選び方も解説
企業内保育所とは、主に企業の従業員の子どもを預かる施設。行事や書類業務が少なく、少人数の子どもの成長を見守りながら、やりがいを感じる保育士さん多数!認可保育園との違いを「比較表」で解説し、仕事内容や実...

託児所とは?保育園との違いや施設の種類、働くメリットや給料についてわかりやすく解説
託児所とは、さまざまな形態の認可外保育園のことを指します。主に企業内や病院で行われる小規模保育や、商業施設内に開設されている一時保育などがあたりますが、保育士さんとしては、一般的な園との違いや働きやす...

保育士の年度途中退職は「無責任」ではない!法律で守られた権利と円満退職に向けた5ステップ
「担任だから年度途中で辞められない」と自分を責めていませんか?実は、保育士の途中退職は法律で認められた正当な権利です。今回は就業規則より優先される「民法の知識」や、円満退職に向けた5ステップ、実際に年...

保育士をサポート・支える仕事特集!保育補助や事務、運営スタッフなど多様な職種を紹介
保育士のサポート役として働きたいという方はいませんか?保育補助や事務、本社勤務の運営スタッフなどさまざまな仕事があるため、保育士さんを支える仕事を一挙紹介!異業種である保育士人材のキャリアアドバイザー...

保育士を辞める!次の仕事は?キャリアを活かせるおすすめ転職先7選!転職事例も紹介
保育士を辞めたあとに次の仕事を探している方に向けて、資格や経験を活かせる仕事を紹介します。ベビーシッターなど子どもと関わる仕事はもちろん、一般企業での事務職や保育園運営会社での本社勤務といった道も選べ...

病院内保育とは?働くメリットや1日のスケジュール、一般的な保育施設との違いについて紹介!
病院内保育とは、病院や医療施設の中、または隣接する場所に設置されている保育園のことです。保育園の形態のひとつであり、省略して院内保育と呼ばれることもあります。転職を考えている保育士さんの中には、病院内...

フリーランス保育士として自分らしく働くには。働き方、収入、仕事内容からメリットまで解説
保育園から独立して働くフリーランス保育士。具体的な仕事内容や働き方、給料などが気になりますよね。今回は、特定の保育施設に勤めずに働く「フリーランス保育士」についてくわしく紹介します。あわせて、フリーラ...

保育園の調理補助に向いてる人の特徴とは?仕事内容ややりがい・大変なこと
保育園で働く調理補助にはどのような人が向いてるのでしょうか。子どもや料理が好きなど、求められる素質を押さえて自己PRなどに活かしましょう。また、働くうえでのやりがいや大変なことなども知って、仕事への理...

子どもと関わる看護師の仕事10選!保育園など病院以外で働く場所も紹介
子どもに関わる仕事がしたいと就職・転職先を探す看護師さんはいませんか?「小児科の経験を活かして保育園に転職した」「看護師の資格を活用してベビーシッターをしている」など保育現場で活躍している方はたくさん...

保育士から転職!人気・おすすめの異業種20選。経験を活かす仕事ランキングや保育士以外の業種を紹介
保育士として働いていると、「保育士以外の仕事にチャレンジしてみたい」「異業種へ転職したい。事務・販売...保育士資格は活かせる?」などと考える方はいませんか?「保育士経験しかないけれど大丈夫?」と迷う...

【保育士の意外な職場30選】一般企業・病院からフリーランスまで!珍しい求人総まとめ
保育士資格を活かして働ける意外な職場は多く、病院、一般企業、サービス業などたくさんあります!今回は、保育園以外の転職先として人気の「企業内・院内保育」から異業種の「フォトスタジオ」「保育園運営本部」ま...

【2026年最新版】幼稚園教諭免許は更新が必要?廃止や有効期限切れの場合の対処法をわかりやすく解説
幼稚園教諭免許更新制については、2022年7月1日に廃止されました。以降は多くの教員免許が「更新不要・期限なし」として扱われるようになりました。ただし、制度廃止前にすでに失効していた免許状には、再授与...

保育士が児童発達支援管理責任者(児発管)になるには?実務経験や要件、働ける場所など
保育士の実務経験を活用して目指すことができる「児童発達支援管理責任者(児発管)」について徹底解説!多くの障がい児施設で人材不足が続いているため、児童発達支援管理責任者(児発管)を募集する施設が多数!2...

幼稚園教諭からの転職先18選!資格を活かせる魅力的な仕事特集
仕事量の多さや継続して働くことへの不安などを抱え、幼稚園教諭としての働き方を見直す方はいませんか。幼稚園教諭の転職を検討中の方に向けて、経験やスキルを活かせる18の職場を紹介します。保育系の仕事から一...

【2026年最新】放課後児童支援員の給料はいくら?年代別の年収やこの先給与は上がるのかを解説
放課後児童クラブや児童館などで働く資格職「放課後児童支援員」の平均給料はいくらなのでしょうか。放課後児童クラブで働く職員は資格の有無を問わず「学童支援員」と呼ばれ、給与が低いイメージがあるようですが、...

【2026年最新】保育士の給料は本当に上がる?正社員やパートの昇給額や「上がらない」と感じてしまう理由
「処遇改善で給料が上がるって聞いたのに、実感がない…いつ上がるの?」そんな声が、保育現場から聞こえる中、政府は保育士の人件費を10.7%引き上げるために、処遇改善制度を新たにスタート!2025年4月か...

私って保育士に向いていないかも。そう感じる人の7つの特徴や性格、自信を取り戻す方法
せっかく保育士になったのに「この仕事に向いていないのでは?」と不安を抱いてしまう方は多いようです。子どもにイライラしたり、同僚や保護者と上手くコミュニケーションが取れなかったりすると、仕事に自信が持て...

ベビーシッターとして登録するなら「キズナシッター」を選びたい理由トップ5
ベビーシッターとしてマッチングサービスに登録する際に、サイト選びに悩んでいる方も多いのではないでしょうか。収入や働き方の安定性、サービスごとの特徴や魅力も気になりますよね。本記事ではそんななか「キズナ...

子育て支援センターで働くには?職員になるための資格や保育士の役割・仕事内容をわかりやすく解説!
子育て支援センターとは、育児中の保護者と子どもをサポートする地域交流の場。保育士経験者は資格を活かして働けるため、転職先のひとつとして考えることも大切です。今回は、職員になるための資格や保育士の役割、...

ベビーシッターになるには?資格や仕事内容、向いている人の特徴
ベビーシッターになるにはどうすればいいのでしょうか?まずは必要な資格やスキルをチェックしましょう。ベビーシッターは働く時間や場所を柔軟に調整できる場合が多く、副業としても人気です!初めてでも安心してベ...

【2026年最新】子育て支援員とは?資格取得の方法・研修、仕事内容などについて解説
「子育て支援員」は、保育や福祉の現場で子どもたちの成長を支える重要な資格です。2026年現在、放課後児童クラブや保育園では人材不足が続いており、子育て支援員のニーズはますます高まっているようです。この...

【2026年版】保育士の転職時期はいつ?年度途中の退職・4月入職のスケジュール
「そろそろ転職したいけれど、いつ動くのが一番いいんだろう…?」そんな不安を感じている保育士さんにとって、安心して転職を進められるベストタイミングは4月(=3月末退職)です。今回は、4月転職が最適な理由...

【2026年版】幼稚園教諭免許の更新をしていない!期限切れや休眠状態の対応、窓口などを紹介
所有する幼稚園教諭免許が期限切れになった場合の手続きの方法を知りたい方もいるでしょう。更新制の廃止も話題となりましたが、更新していない方は今後の対応方法をくわしく把握しておくことが大切です。今回は、幼...

【2026年最新】調理師の給料、年収はどれくらい?仕事内容や求人、志望動機なども徹底解説
子どもたちが毎日口にする給食やおやつを作る保育園の調理師。保育園で常勤として働く場合、年収は300万円以上が相場のようです。さらに、保育園調理師なら成長する子どもの身体づくりを助ける存在として、やりが...

インターナショナルスクールに就職したい保育士さん必見!給料や仕事内容、有利な資格とは
保育士さんが活躍できる場所のひとつとしてインターナショナルスクールがあります。転職を検討するなかで、英語力は必須なのか、どんな資格が必要なのかなどが気になるかもしれません。今回は、インターナショナルス...

【2026年】保育士の借り上げ社宅制度とは?自己負担額と同棲・結婚後の条件を解説
保育士さんの家賃負担を軽減する「借り上げ社宅制度」。2025年度の制度改正で利用条件が変わり「制度がなくなる?いつまで使える?」「結婚してもOK?」といった疑問や不安も多いようです。本記事では、制度の...

児童館職員になるには?必要な資格や仕事内容、給料
児童館は、地域の子どもたちへの健全な遊び場の提供や子育て家庭の育児相談などを行なう重要な施設です。そんな児童館の職員になるにはどのような資格が必要なのかを解説します。また、児童館の先生の仕事内容や20...

病児保育とはどのような仕事?主な仕事内容や給与事情、働くメリットも解説
病児保育とは、保護者の代わりに病気の子どもを預かる保育サービスのことを言います。一般的に、風邪による発熱などで保育施設や学校に通えない子どもを持つ保護者が利用します。今回は、そんな病児保育の概要を詳し...

【2026年度】保育士の給料と年収は今後どうなる?処遇改善の昇給額と採用で年間30万円支給する地域も紹介!
保育士は「給料が低い」と言われるなか、処遇改善で人件費が10.7%引き上げられました。2025年度に公表された統計では、正社員の平均年収は約407万円、パートの時給1,370円へ改善。ただし「手取りが...

保育園の事務仕事がきつい理由TOP5!仕事内容や給料、業務で楽しいと感じることも紹介
保育園で事務職の仕事を知りたい方必見!仕事に就いてから後悔しないように、今回は、保育園事務の仕事内容や業務がきつい理由・楽しいと感じることTOP5をわかりやすく紹介します。給料や待遇、採用に向けた面接...

新生児介護職員として無資格で働くには?病院や乳児院などでの仕事について
新生児介護職員など、新生児のケアに携わる仕事に関心を持つ方には、無資格でも働けるのか気になる方がいるかもしれません。基本的に「新生児介護職員」という職種はありませんが、新生児のケアに関わる仕事を指すこ...

病児保育士になるには?必要な資格や資格の合格率、給料事情を解説
体調の優れない子どもを保護者の代わりに預かる病児保育士。そんな病児保育士になるには、一体どうすればよいのでしょうか。今回は病児保育士になるために必要な資格などを紹介しつつ、病児保育士として働ける職場や...

乳児院とは?果たす役割や子どもの年齢、現状と今後の課題など
乳児院とは、なんらかの理由で保護者との生活が困難な乳児を預かる施設です。一時保護やショートステイで滞在する場合もあり、保育士の求人もあります。そんな乳児院とはどんな施設なのか、厚生労働省の資料をもとに...

新しい働き方「総合職保育士」とは?仕事内容や働くメリット、給料事情など
総合職保育士という働き方をご存じでしょうか?近年注目されはじめている新しい働き方で、保育士以外の職種にキャリアを転換しやすいことが特徴です。今回は、総合職保育士について、仕事内容や給料事情、キャリアコ...

乳児院で働く職員の一日の流れは?仕事内容や年間行事、早番~夜勤の勤務時間まで
乳児院で働く職員の一日の流れや仕事内容とはどのようなものなのでしょうか。乳児院は24時間365日子どもたちを養育する施設であることから、交代制の勤務形態がほとんどです。今回は乳児院で働く職員の一日の流...

乳児院の給料はいくら?職員の資格別に平均給与を確認しておこう
乳児院は乳幼児期に適切な養育が受けられない乳児を保護し、健全な育成を図るための施設であり、医師や看護師、保育士などさまざまな資格を持つ職員が働いています。そんな乳児院の給料事情について、詳しく知りたい...

乳児院でボランティアとして活動したい!活動内容やボランティアを探す方法を紹介
乳児院は乳幼児期に適切な養育が受けられない乳児を保護し、健全な育成を図るための施設です。社会的に大きな意義のある施設だからこそ、その力になりたいとボランティアとしての活動を希望する場合もあるでしょう。...

保育士さんが乳児院を辞めたい理由。働き方や悩み、ひどいと感じる時とは
乳児院で働く保育士さんが辞めたいと感じるのはどんなときでしょうか。勤務体制、保育の内容などさまざまな問題で、ひどい・つらいと思うことがあるかもしれません。また、保育をする上で乳児院ならではの難しさもあ...

乳児院で働く看護師とは。役割や仕事内容、給料事情など
看護師資格を活かして働ける転職先の一つとして、乳児院を検討している方もいるかもしれません。しかし、そもそもどんな施設で、病院や保育園での仕事内容とどう違うのかなど気になりますよね。今回は、乳児院で働く...

保育において欠かせない養護とは?乳児期と幼児期のねらい
保育における養護は、子どもたちの健康管理を担うという役割だけではなく、子どもたちの心身の健やかな成長を支えるという大切な要素も含まれています。けれども、具体的な内容や対応の仕方について戸惑う方も多いの...

保育園における乳児保育について知っておこう。概要や保育士さんの役割
保育園で行なう乳児保育とは、どういったものなのでしょうか。乳児保育に興味を持っていながら、自分に向いているのか気になっている人もいるでしょう。今回は、保育園における乳児保育について、概要や保育士さんの...

乳児保育に興味がある保育士さん必見!やりがいや大変なこと
乳児保育に興味があるという保育士さんもいるのではないでしょうか。乳児保育とはどのようなものなのか特徴などをおさえておくと、就活の際に役立つかもしれません。今回は乳児保育を担当する保育士さんが感じる、や...

乳児向けのふれあい遊び。ねらいや効果、保育園で楽しめる人気の手遊び歌
乳児クラスでのコミュニケーションにぴったりなふれあい遊び。0歳児や1歳児、2歳児の子どもたちは、保育士さんとスキンシップを取りながら、わらべうたや手遊び歌を楽しんでくれるかもしれません。今回は、保育園...

【35選】乳児向けの室内遊びまとめ。保育のねらいや、ゲーム・製作など春夏秋冬のアイデア
雨の日や冬の寒い日、夏の日差しの強い日などは、保育園で乳児さんと室内遊びを楽しみましょう。今回は乳児(0歳児・1歳児・2歳児)クラスで楽しめる運動やゲーム性のある遊び、製作遊びのアイデア35選を紹介し...

保育士に人気の乳児保育。0~2歳児の赤ちゃんとの接し方や、働く上での魅力とは?
0~2歳児の赤ちゃんのみを対象とした乳児のみの保育園、なかでも小規模保育が、ここ数年で驚くほど増加しているのはご存じでしょうか?2017年3月の時点で設置数は2,553件。ここ2年間で約1.5倍ほど増...

乳児保育の現場での子どもの名前を呼ぶねらいとは?名前を覚えるための遊びも紹介
乳児保育の現場で、日常的に子どもの名前を呼びますが、そこには子どもの安心感を育み、信頼関係を築くための重要な役割が込められています。そもそも名前を呼ぶという行為は、子どもにどのような影響を与えるのでし...

資格なしで新生児ケアアシスタントとして働くには?新生児ケアに携わるために知っておきたいこと
保育関係の資格なしでも「新生児ケアアシスタント」という仕事に興味を持つ方がいるかもしれません。新生児ケアに関わる職種はさまざまありますが、実際には資格が必要な職種が多いのが現状です。今回は、資格なしで...

認定病児保育専門士になりたい!資格の取り方や役割など
病児保育における専門的な知識を持つ認定病児保育専門士。この資格を取得することで、保育士としてのキャリアが広がり、病児・病後児保育室などの活躍の場が一層増えるでしょう。この記事では、認定病児保育専門士の...

認定病児保育スペシャリストの資格の活かし方!就職に有利な仕事は?
認定病児保育スペシャリストの資格を活かして働きたいと考えている保育士さんもいるでしょう。保育士として、資格で得た知識を使える場面もあるかもしれません。今回は、認定病児保育スペシャリストの資格を持ってい...

【例文あり】病児保育士に転職したい!志望動機の書き方や働くメリットなど
発熱や病気で、保育園に登園できない子をスポットで預かるのが「病児保育施設」です。そんな病児保育士へ転職したい!でも、どうアピールすればよい?と、志望動機でつまずく保育士さんもいるようです。今回は、病児...

職場としての認定こども園の種類、保育士の働きやすさ
「認定こども園」とは、保育所と幼稚園それぞれの良さを生かした施設のことです。なんとなく知っていても、具体的な定義や仕事内容まで説明できる保育士さんは少ないのではないでしょうか?今回のコラムでは、認定こ...
- 同じカテゴリの記事一覧へ
<汐見稔幸先生・プロフィール>
1947年大阪府生まれ。 2018年3月まで白梅学園大学・同短期大学学長を務める。
東京大学名誉教授・日本保育学会会長・国保育士養成協議会会長・白梅学園大学名誉学長
保育所保育指針の改定に関する検討を行った社会保障審議会児童部会保育専門委員会委員長を務めた。
また現在、厚生労働省子ども家庭局長が学識経験者等を参集した「保育所等における保育の質の確保・向上に関する検討会」で座長を務める。
専門は教育学、教育人間学、保育学、育児学。
一般社団法人家族・保育デザイン研究所代表理事。
保育についての自由な経験交流と学びの場である臨床育児・保育研究会を主催。
保育者による本音の交流雑誌『エデュカーレ』の責任編集者を務め、『10の姿で保育の質を高める本 (これからの保育シリーズ)/汐見 稔幸 (著)中山 昌樹(著)(出版社 風鳴舎)』『さあ、子どもたちの「未来」を話しませんか/汐見稔幸 (著)おおえだけいこ(イラスト)(出版社 小学館)』などの書籍執筆や講演会など、全国を飛び回り精力的に活動している。
<取材・執筆・撮影>保育士バンク!編集部

保育士バンク!の新着求人
お住まいの地域を選択して、最新の求人情報をチェック!


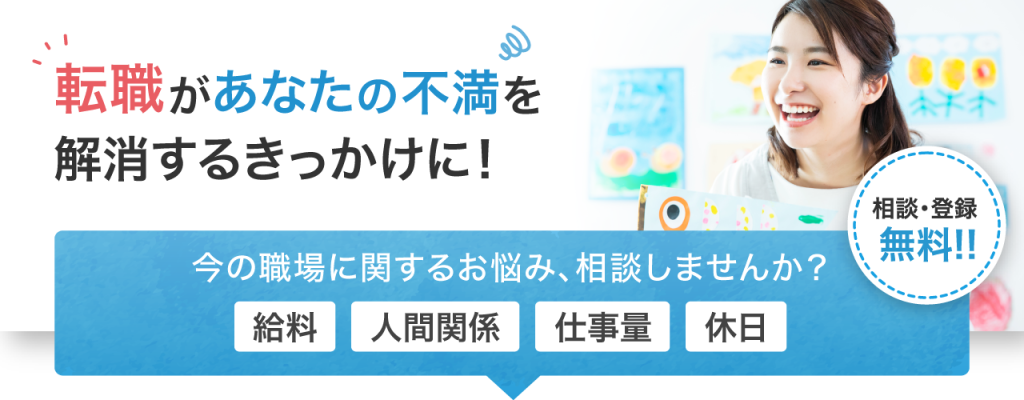





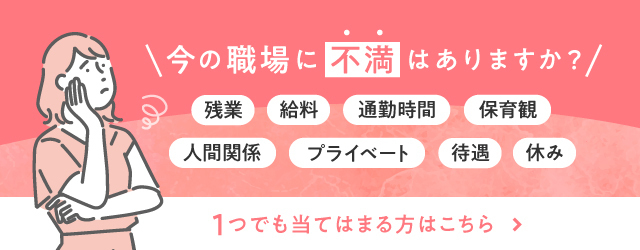
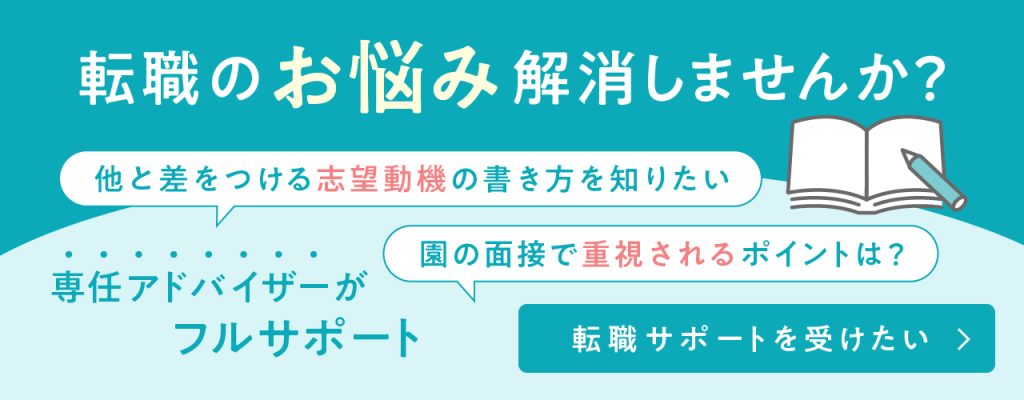
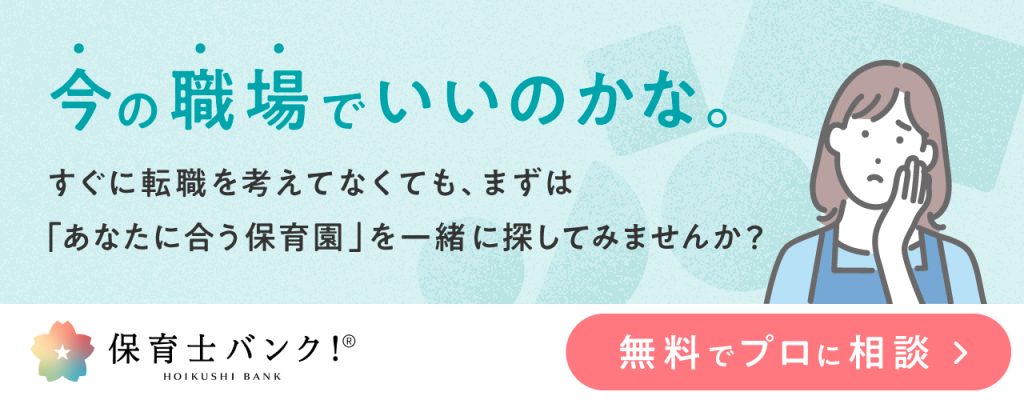
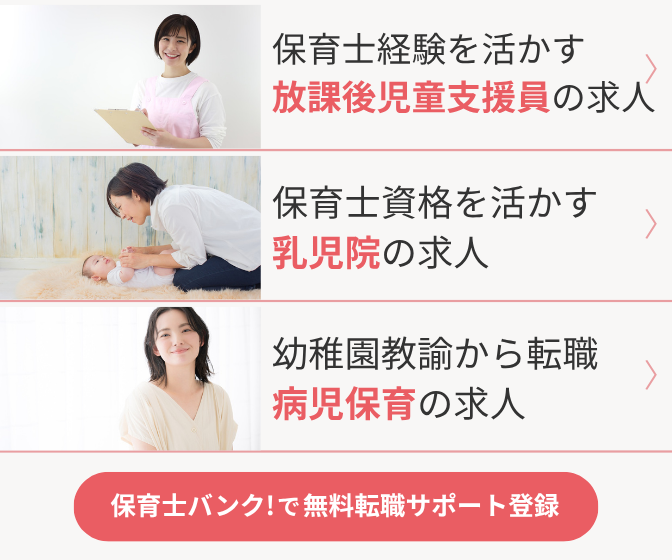
























/campaign/0004/DZ7TWBcJ3MWmgU6JV1RVa7zbReTDn5CSzSupdV30q4TVPaApz5heM6bnqp1TJkqs)