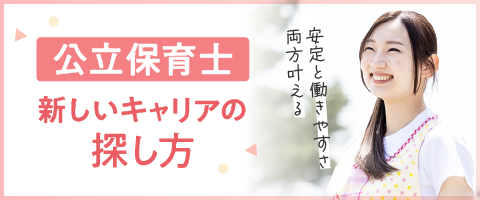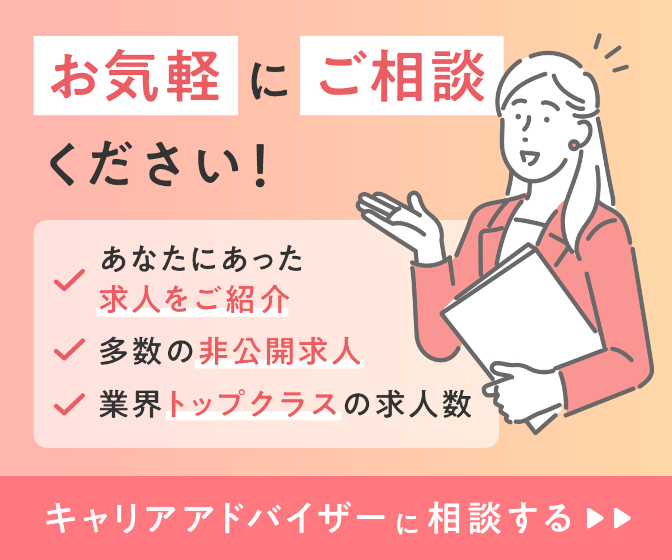保育園で地震が起きた場合に備えて、子どもに地震の意味や逃げ方をわかりやすく説明する必要があるでしょう。防災意識を高めるうえで、日頃から避難訓練時の約束事を確認することも大切です。今回は保育士さんが子どもに対して、地震の意味や逃げ方を説明する方法を紹介します。お約束事で使われる「おかしもち」の伝え方もまとめてみました。


maroke/shutterstock.com
保育園で地震や避難方法の説明をしよう
近年、日本では地震が起きる回数が増えており、災害に備えた対策が求められています。
保育園においても子どもたちの命を守るために、定期的に避難訓練を行うことが大切になります。その際に、保育士さんは地震の意味や逃げ方について、園児にわかりやすく説明する必要があるでしょう。
なかには、地震の意味をよく知らない子どもたちもいるため、難しい言葉を使わずにクイズや絵本などを活用することがポイントになります。
また、避難訓練時に約束事を話す際、「おかしもち」というワードを使う保育園も多いのではないでしょうか。
地震の意味を説明する方法や「おかしもち」の伝え方を把握し、防災に向けて取り組んでいきましょう。
子どもに地震について説明する方法
まずは、子どもに地震の意味を説明する方法を紹介します。
演劇
子どもに地震について説明する際に、保育士さん同士で演劇を行い、披露するとよいかもしれません。
「園児側」と「避難の誘導側」に分かれ、「地震ってこんなに揺れるんだね」「こわくて逃げられないよ」など、園児が感じることを意識して脚本を作成しましょう。
クイズ
子どもたちに地震についてクイズを出題し、関心をもってもらえるように、工夫するとよいかもしれません。例題を記載するので、参考にしてみてくださいね。
例題1:「みんな地震っていう言葉は聞いたことがあるかな?」
「テレビで見たことあるー」「揺れるんだよね、こわいね」など子どもたちからさまざまな意見が返ってくることが考えられます。園児の気持ちに寄り添いながら、地震についてどのような印象を持っているのか、耳を傾けてみましょう。
例題2:「地震は地面がゆれて歩いたり、立ったりすることも難しいものです。どうしてそうなのるのかな?」
子どもたちから「だれかが保育園を揺らしているんじゃない?」など面白い言葉が返ってきそうですね。
ここで下の例のように、地震について子どもたちへわかりやすく伝えてみましょう。
「地震がなぜ起こるのかお話するね。
みんなが立っている地面の奥にある岩は実は動いているんです。少しずつ動いているから揺れを感じないことがほとんどだよ。だけど、岩が大きく動くとそれがみんなの立っている所に伝わって、とっても揺れることがあります。それを「地震」といいます。
保育園の本が棚から飛び出したり、ドアが壊れたりしてみんなにぶつかったらケガをしてしまうこともあります。
だから、地震が起きたらみんなで先生や園長先生のお話をきちんと聞いて、逃げるときの練習をしようね。」
上記のように、子どもたちにわかりやすい言葉を選んで地震の話をしていきましょう。
“揺れる”ということがどういうことなのかわからない子どもたちもいるかもしれません。地震がきて揺れたときの様子を保育士さんが演じたり、イラストで説明したりすると、伝わりやすいでしょう。
絵本や紙芝居
地震について伝える際に、地震を題材にした絵本や紙芝居を活用することもひとつの方法です。イラストがえがかれているため、子どもたちもイメージしやすいでしょう。
保育士さんが読むときは登場人物になりきり、声の強弱を意識するなど、地震に対して興味や関心を抱くように工夫できるとよいですね。
簡単1分登録!転職相談
保育士・幼稚園教諭・看護師・調理師など
保育関連の転職のご質問や情報収集だけでもかまいません。
まずはお気軽にご相談ください!
【地震の避難訓練】子どもに「おかしもち」を説明する方法

milatas/shutterstock.com
「おかしもち」という言葉に耳慣れないと感じる方もいるかもしれませんが、災害時に子どもたちに避難訓練のお約束事をわかりやすく伝えられる便利な言葉です。
おかしもちの一つひとつの言葉の意味は以下の通りです。
- お「友だちをおさない」
- か「ひとりで駆けない(走らない)」
- し「友だちとしゃべらない」
- も「元の場所に戻らない」
- ち「危ないところに近づかない」
「おかしもち」は災害時の大切な約束ごとの合言葉のひとつになります。保育室に言葉を掲示したり、イラスト入りで紹介したりすると子どもたちが覚えやすいかもしれません。定期的に朝の会や帰りの会などで約束事を確認する園もあるようです。
ここで、「おかしもち」を子どもたちにわかりやすく説明する方法を紹介します。
「お」:押さない
「じしんが起こったときは揺れて、保育園の建物がくずれてしまったり、上から物が落ちてきたりすることが考えられます。机やテーブルの下に隠れると、身体を守ることができることが多いです。そのときは、周りの友だちや先生を押したり、ぶつかったりすると転んでケガをしてしまうから気をつけようね。
揺れがおさまったらホールや保育園のお庭に逃げることもあるでしょう。そのときも他の人にぶつからないようにしようね。」
「押さない」の意味を説明するときは、友だちや先生にぶつからるとケガをしてしまう可能性を伝えましょう。地震が起きた場合にどのような危険性があるのか、具体的に話すことでイメージが沸きやすいでしょう。
「か」:駆けない(走らない)
「地震が起きると地面が揺れてこわくて走りたくなることもあるかもしれません。そのときはまずは走らないで、ダンゴムシのポーズになると頭や身体を守ることができます。先生も『ダンゴムシになるよ!』とお話するから、変身してみよう。※先生が分かりやすいようにダンゴムシのポーズをとる
揺れがおさまったらホールや保育園のお庭に逃げることもあるでしょう。走らずに先生や園長先生のお話をよく聞いて動こうね。」
ダンゴムシのポーズは後ろで両手を組み、足をそろえて正座の形をして身をかがめ、小さく身体を丸めるポーズのことをいいます。
先生が見本になり、ポーズをとることで子どもたちに伝わりやすくなります。揺れがおさまってこわくなり、すぐ走り出す子もいるかもしれません。「まだダンゴムシポーズのままでいてね。」など子ともにわかりやすいように、伝え方を工夫しましょう。
「し」:しゃべらない
「地震が起きると、「どうしよう!」「こわいよ!○○ちゃん」としゃべりたくなることもあるよね。でも、友だちとしゃべると先生のお話が聞こえなくなって、どんな風に動けばよいのかわからなくなることもあります。
それに給食室で料理をしているときに地震が起きたら、火事になってけむりがたくさん出るかもしれません。
しゃべっていると口の中にけむりが入って、苦しくなることもあるから気をつけようね。」
地震が起きたときにしゃべるとどのようなリスクがあるのか、子どもたちにわかりやすい言葉で伝えましょう。火事になった場合も伝え、身体を守る大切さを話せるとよいですね。
「も」:もどらない
「地震が起きて揺れがおさまったら、ホールや保育園のお庭に逃げることもあります。逃げたあとに『ジャンバーをわすれた。』『バックをとりにもどらなきゃ!』とお部屋に戻りたくなることもあるかもしれません。
でも、戻ったときにまた地震がきてケガをすることもあります。先生や園長先生のお話をよく聞いてから動くようにしようね。」
子どもたちが不安にならないように、なぜお部屋に戻ってはいけないのかをしっかり説明するようにしましょう。
「ち」:ちかづかない
「地震が起こると保育園にある棚が壊れたり、いろいろなものが落ちてきたりすることがあるかもしれません。そこに近づくと転んでケガをして危ないよね。
それに給食室から火が出て、火事になることもあります。危ないところは先生が説明するから、近づかないようにしようね。みんなでケガをしないように気をつけよう!」
実際に地震が起きたときに、子どもたちは危険な場所が分からずに走り出してしまうこともあるでしょう。地震が起きるとどのような場所が「危ない」のか、具体的に話をするとよいかもしれません。
このように防災対策のひとつとして、保育園で子どもたちに向けて「おかしもち」の意味を丁寧に説明しましょう。上記を参考に説明してもよいですし、保育士さん同士で伝え方のアイデアを出し合うなど、工夫できるとよいですね。
保育士・幼稚園教諭・看護師・調理師 etc.無料転職サポートに登録子どもに地震をわかりやすく説明して防災意識を高めよう
地震が起きたときに子どもたちが落ち着いて行動できるように、避難訓練ではお約束事を説明することが大切になります。
園児に「ダンゴムシのポーズをとる」「机やテーブルの下に入って身を守る」など具体的に身を守る方法を伝え、わかりやすい言葉で話せるとよいですね。
また、職員同士で子どもたちの誘導方法などを定期的に確認し、災害に備えることも重要です。
保育園で地震が起きた場合を想定し、避難の方法や子どもへの声かけの仕方をしっかり考えて、防災意識を高めていきましょう。
関連記事:9月1日は防災の日。保育園での避難訓練のポイントや子どもたちへの伝え方/保育士バンク!

保育士バンク!の新着求人
お住まいの地域を選択して、最新の求人情報をチェック!


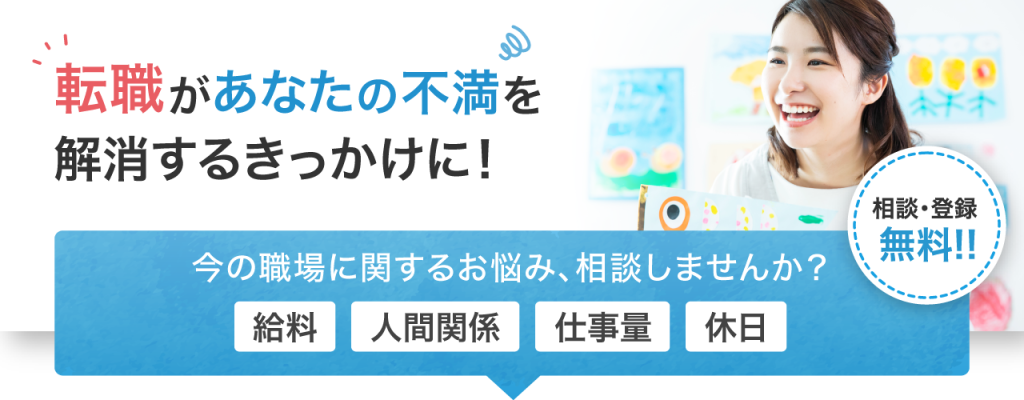





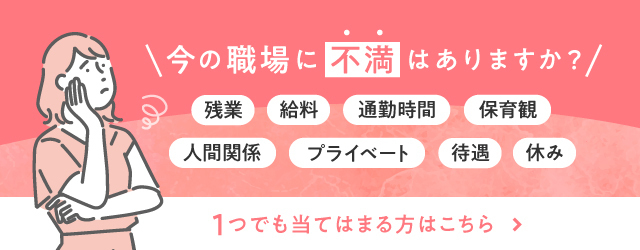
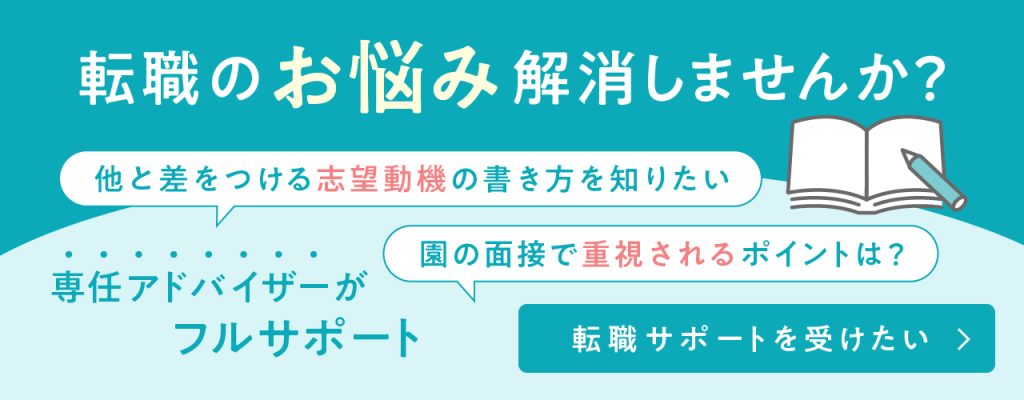
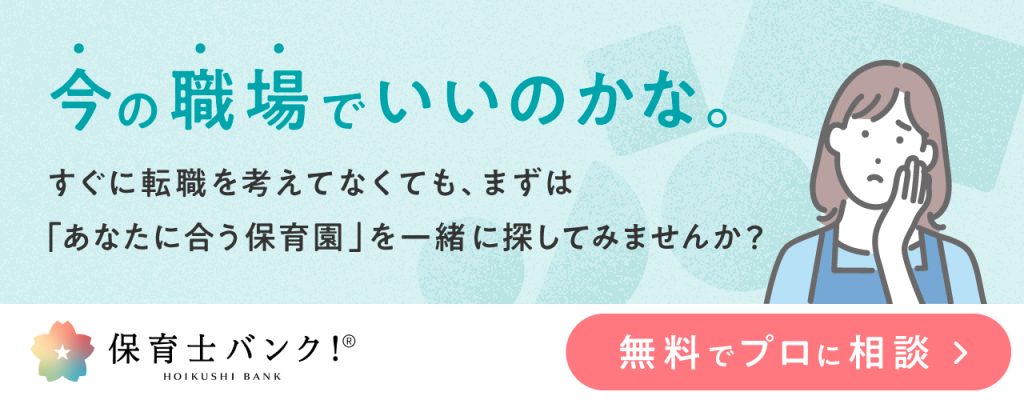
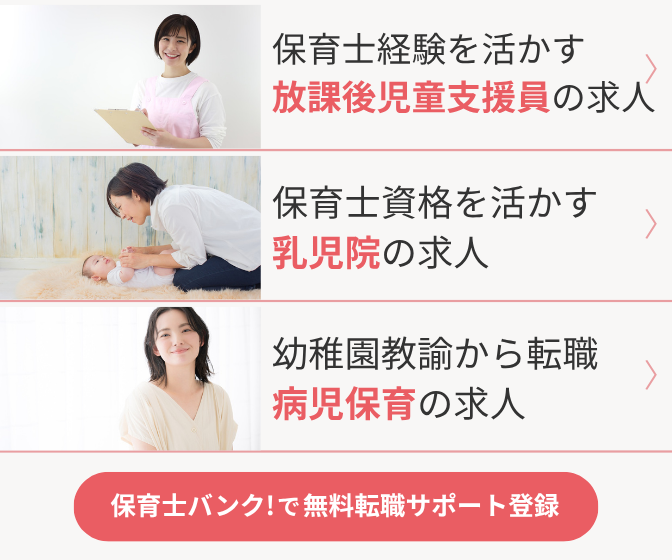



































/campaign/0004/DZ7TWBcJ3MWmgU6JV1RVa7zbReTDn5CSzSupdV30q4TVPaApz5heM6bnqp1TJkqs)